あなたたちに伝えたい「人生で大切なこと」
Z会にゆかりの深い加地伸行先生から、中高生のみなさんへのメッセージをお届けします。
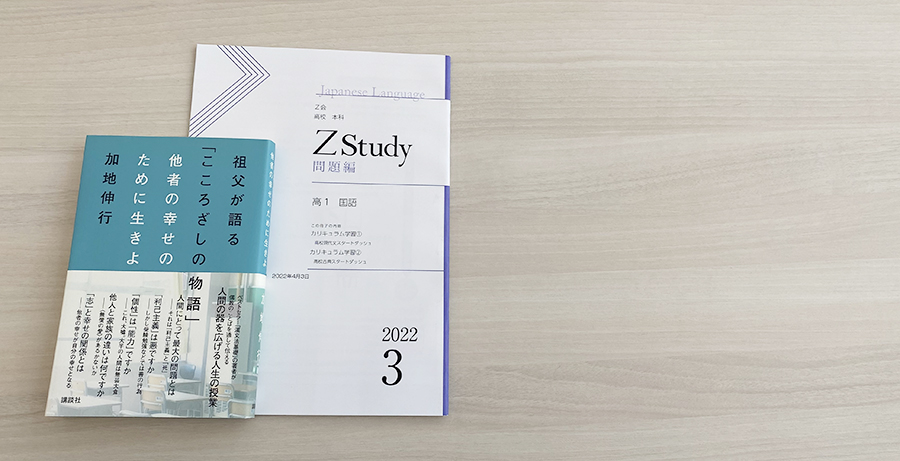
Z会への信頼
Z会――私が受験生のころは、もともとの名前、すなわち「実力増進会」でした。そこから、のちに「Z会」というふうな呼び方に変わって現在に至っています。
実力増進会――私にとっては、とてもなつかしい名称です。そのころ、と言えば、現在八十五歳の私からすれば、約七十年も昔のことですが、そのころ、私は浪人をしていました。
しかし、予備校には通っていませんでした。その理由は簡単です。家が貧しかったからです。それが最大の理由です。
そのとき、私を支えてくださった方々が、実力増進会の添削者の先生方でした。
その添削の先生にはいろいろな方がおられました。そのうちの或る方は、小説家志望の方でした。そのようなことがなぜわかったかと言いますと、こういうわけです。
国語の問題でした。その或る文章について、私が私なりの解釈をしましたところ、真向から「それはおかしい」と批評されたのです。しかし、負けずぎらいの私は、反論しました。もちろん私信を差し出しまして、です。
それに対して、お返事をお手紙でいただきました。というようなことで、親しくなりました。
そして、受験の年の正月でした。その先生が、自分は大阪出身なので、正月に大阪に帰るので会おう、とおっしゃったのです。
お会いしました。ちょうど石原慎太郎が小説『太陽の季節』でデビューした年でした。その小説を中心に、話しました、論じました、何時間も。そのころの喫茶店はそういう議論のできる雰囲気だったのです。
その時、その先生が小説家志望だったことを知ったのです。そのときのわれわれ二人の「慎太郎論」は、「なんだ、アイツ」でした。
と話してきますと、遠い昔のことを次々と想い出します。そうした私の想い出の中に、実力増進会(Z会)がしっかりと生きています。そしておそらく、Z会のその〈在りかた〉――すなわち〈心の結束〉がZ会への厚い信頼を作ってくれているのでしょう。
あなたに語りたい
私は、かつて増進会すなわちZ会の会員でした。今もZ会とは深い関わりがあります。
もっとも、私は老人です。あなたたち中学生・高校生は若い。私から見れば孫のような感じです。そういう若い人たちが、これからの人生を生き抜いてゆく立場にあるのを見ますと、私の気持ちは、語りかけてあげたい、生きてゆくことの大切さ、面白さ、悲しさ、人間としての在りかた、などなど、ということでいっぱいです。
以前、私はZ会のみなさんに語りかけた連載をまとめ、出版したことがありました。書名は『祖父が語る「こころざしの物語」 他者の幸せのために生きよ』(講談社)です。
今回、再びあなたたちに、いろいろなテーマの下に、語りかけたいと思います。私が祖父、あなたたちが孫という設定で進めたいと思います。
「科挙」――中国で行われた選抜試験
受験――このことをめぐる話は、山ほどあります。私は中国の思想についての研究者ですので、その仕事の関係で、中国の受験のことについても、一応のことは心得ています。
中国の王朝の歴史は古いのですが、受験のことが表に現れることは、とくにはありませんでした。しかし、隋王朝の末ごろ、「科挙」という官吏登用試験が行われるようになりました。西暦六〇〇年前後のことです。
同六〇七年には、遣隋使として日本から小野妹子が海をわたって隋の都へ行きました。そのころです。
この科挙試験が行われる前までは、官吏の選び方がなかったものですから、官吏(公務員)の質がよくなかったのです。中には、金銭を積んで贈り、官僚になった者もおりました。そういう者が官僚になりますと、汚職をして金銭を溜めこむのでした。
そこで、ちゃんとした試験を行い、その合格者を官吏にするという試験を新しく実行しました。科目ごとの「科」、選び取るの「挙」、併せて「科挙」という名称の試験のことです。
この科挙試験の目的は、公正な人間を採用することでした。
そのため、採点は厳密でした。もちろん、不正がありましたら処罰されました。ですから、受験生も自分の努力が報われることを頼みとして一生懸命に勉強しました。
日本に伝わった科挙
この科挙は、日本におきまして同様の目的で始められたのですが、続かず、なくなってゆきました。その理由はこうです。大豪族の数が中国ほど多くなかったため、権力争いは少数の豪族の争いで決着がついており、朝廷の支配が及ばなかったからです。ですから、日本では奈良朝以来の統一国家ではありましたけれども、地方豪族がしだいに大きくなり、その中からやがて鎌倉幕府が生まれ、朝廷は政治権力を失います。その地方勢力と幕府とで政治が行われるようになって、明治維新に至ります。朝廷は政治権力を失いましたが、奈良朝以来の律令制度は残ってゆきましたので、地方豪族への任命権は残り、それを執行していました。ですから、大名の代替わりがありますと、その地域の「長(たとえば「薩摩守」)に任ず」という承認書を与える権威は朝廷に残りました。
このように、日本では科挙はなくなり、明治以後になって官僚採用試験が行われるようになりました。これらの話、いつか改めてお話ししましょう。
現代の教育と受験というありかた
受験――これは、明治から生まれた新しい形のものです。それが現代の教育や受験とどのようにつながっているのか、次回から述べてゆきます。自分の努力で道が開ける「受験」。それを信じてください。私は、あなたのそばでアドバイスを続けてゆきます。

Z会顧問 大阪大学名誉教授
加地伸行(かぢ のぶゆき)
1936年大阪生まれ。1960年京都大学文学部卒業。文学博士。高野山大学助教授、名古屋大学助教授、大阪大学教授、同志社大学フェローを経て、現在、立命館大学研究顧問、大阪大学名誉教授。専門は中国哲学。六十年来、Z会と深い関係があり、今日に至っている。

