いわゆる「オンライン授業」のようなICTを使った授業が行われるようになり、「新しいかたちの学習」に取り組むことが増えました。
これまで一般的なものだと考えていた学校で行われる一斉授業(対面授業)を経て、今後、より一般的になっていくであろうICTを取り入れた授業に、私たちはどのような姿勢で向き合い、活用し、学びを深めていけばよいのでしょうか。
ICTを学びの場に導入する際の学習環境のあり方について研究されている東京大学大学院 情報学環 学際情報学部山内祐平先生にうかがいました。
いわゆる「オンライン授業」のようなICTを使った授業が行われるようになり、「新しいかたちの学習」に取り組むことが増えました。
これまで一般的なものだと考えていた学校で行われる一斉授業(対面授業)を経て、今後、より一般的になっていくであろうICTを取り入れた授業に、私たちはどのような姿勢で向き合い、活用し、学びを深めていけばよいのでしょうか。
ICTを学びの場に導入する際の学習環境のあり方について研究されている東京大学大学院 情報学環 学際情報学部山内祐平先生にうかがいました。
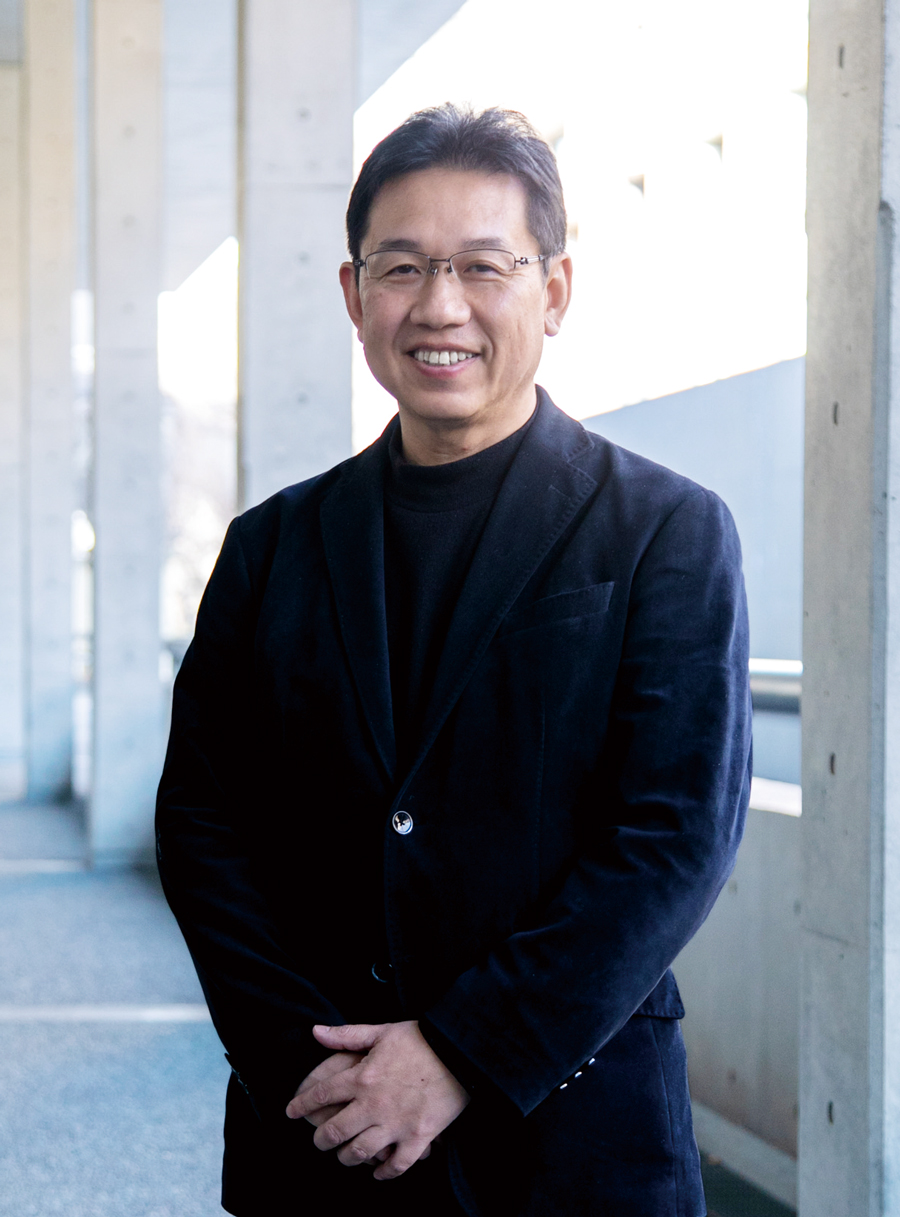
山内 祐平先生
(東京大学大学院情報学環 教授)
1967年愛媛県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程中退。茨城大学人文学部助教授、東京大学大学院情報学環准教授などを経て2014年から現職。「学習環境のイノベーション」を研究テーマに、学習者を積極的に自らの学びをデザインする存在としてとらえ、そのプロセスを支援するための今までにない新しいしくみについて、教育学・デザイン論・教育工学・学習科学などの知見をもとに研究している。著書に、『学習環境のイノベーション』(東京大学出版会)、『デジタル教材の教育学』(編著、東京大学出版会)、『学びの空間が大学を変える』(共著、ボイックス)など、多数。
特殊だったコロナ禍のオンライン授業
―新型コロナウイルスの流行による休校期間中、オンライン授業だったり、紙の課題が指定・配布されたりと、中高生が置かれた環境はさまざまでした。対面授業が受けられない間の学びの状況について、先生はどのように思われましたか?
文部科学省で2020年6月に行った「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における学習指導等に関する状況について」という調査では、各学校でどのような学習方法がとられたかを調べています。これを見ると、休校した公立学校のうち、高等学校で99%、中学校は100%の学校が教科書や紙の教材を活用して学習を行っていますが、同時双方向型オンライン指導を行ったのは、高校で47%、中学校で10%です。この調査では、1回でも行えば実施したとカウントされますから、オンライン授業が広く展開されていたとは言えないでしょう。また、実施した学校においても、初めて取り組む先生が多く、十分なことができたかどうかは疑問が残ります。
今回の休校期間中に各学校で行われたオンライン授業は、学校での対面授業ができず、準備期間も十分にとれない状況で、みなさんの学びを保障するためのしくみとして「普段の授業を代替する」目的で導入されました。これは、コロナ以前からの教育のICT化で考えられていた流れとは異なるもの。まずは、そのことを理解しておいていただきたいと思います。
加えて、学び続けるため、また、学びの効果を高めるための環境を整備するのは、教育委員会や学校、みなさんのご両親といった大人たちの仕事であって、中高生のみなさんに責任はありません。このような臨時の事態においても、すべての中高生が学習を継続でき、その学習効果を高めるしくみを大人たちがしっかりとつくるべきでしたし、間に合わなかった部分については、今後も検討すべき課題だと私は考えます。
ただ、今回「オンライン授業というものがどういうものか」ということを多くの人が体験できたことは非常に大きいことだと思います。ICTを使うとこういう学習ができるんだということが認識されたことによって、今後の学習により積極的にICTを取り入れるという流れがどんどん加速していくと思います。
学校が課した家庭における学習の内容
| 家庭学習の内容 | 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 | 中等教育学校 |
|---|---|---|---|---|
| 教科書や紙の教材を活用 | 100% | 100% | 99% | 100% |
| テレビ放送を活用 | 34% | 47% | 31% | 50% |
| 教育委員会が独自に作成した学習動画を活用 | 23% | 39% | 30% | 50% |
| 上記以外のデジタル教科書やデジタル教材を活用 | 36% | 53% | 51% | 75% |
| 同時双方向型のオンライン指導 | 10% | 17% | 47% | 70% |
―そもそも、ICTを活用した学びとは、どのようなものなのでしょうか?
大きく分けて、3つのパターンがあります。1つめは対面授業にICTを取り入れ、一人ひとりの学びに寄り添う方法です。たとえば、対面授業で先生に一斉に教えてもらいつつ、一人ひとり自分のパソコンやタブレット端末で個々の学習進度に応じた問題に取り組み、学習内容を深めていくような学び方です。
2つめは、対面授業で学んだ知識を持ち寄り、創造的な学習を行うための道具としてICTを利用する方法です。たとえば、正解が一つではない問いや、答えのないような問題に対して、その解決方法をインターネットで調べたり、世界中の学習者とチームを組んで学習するいわゆる「プロジェクト学習」を行うときの道具として、ICTは活用されます。
3つめは、オンラインで映像教材を見て学ぶ方法です。世界中の大学の講義を無料で受けられるMOOC(Massive Open Online Course)と呼ばれる大規模公開オンライン講座があり、東京大学でも、世界中の人を対象に授業を行っていますが、こういった講義の録画で学習したあとに、Web上にある専用の掲示板で質問したり、一緒に講義を受けている仲間と議論するやり方があります。
1つめと2つめは対面授業があることを前提にしていますが、3つめは対面授業を前提とせず、オンラインでのみ学習するのが特徴です。
オンライン授業の課題とは?
―これらのオンライン授業にはどのような課題が考えられますか?
先ほど説明したMOOCを例に考えてみましょう。MOOCのよさは、地理的・空間的なハードルがなく、今いる場所から世界中の大学の最先端の知にふれることができること。オンライン授業のほかにWeb上の掲示板もあるので、同じ関心をもったさまざまな世代の人たちと知り合い、議論することもできます。
一方で、2つ課題があります。1つめは、自分で学習をコントロールしなければならないこと。毎週曜日を決めて映像を見て、わからないところがあれば掲示板で質問・議論し、テストを受けるということを数週間繰り返して修了するしくみなので、自分の学習進度や理解度を客観視しながら目標に向かって進んでいく力が問われます。したがって、学校に比べるとドロップアウトが起きやすい。
2つめは、こういった形態は、新しい知識を身につけるのにはよいのですが、思考力やコミュニケーション力を身につけるには必ずしも向いていない点です。
このように、オンライン授業のみで学ぶことには、可能性がある一方で限界もあります。だからこそ、これからは、対面授業と組み合わせてICTを活用するという「ハイブリッド型」の学習スタイルが主流になると考えています。たとえば、あらかじめ宿題などで映像を見て知識をインプットしておき、対面ではその知識を使った応用の学習を行う「反転授業」は、現在も大学などで行われているハイブリッド型の一つです。これに限らず、さまざまな方法が考えられていくでしょう。
「オンライン授業の学び方」とは?
―では、そのような課題を意識しつつ、今後、オンライン授業が行われた際には、どのように学べばよいのでしょう?
まずは、オンライン授業にしっかりと参加することです。対面授業には、一つの目標やねらいに向かってクラスの仲間とともに向き合い、学ぶというよさがありますが、オンライン授業でも同じです。仲間や先生とともに学ぶという関係性をもちながら授業に参加する。これが基本中の基本です。そのうえで、次のような工夫が必要だと思います。
1つは、オンラインで学ぶための環境を整備すること。具体的には、通信環境とデバイスです。これは、保護者の方にお願いしたいことですが、映像が途切れない速度の回線や、長時間使用でき、体に負担のかからない端末の方が学習がしやすいというのは、言うまでもないことでしょう。こういった環境が整えられるのなら、整えるに越したことはありません。
2つめは、「ながら」をしない、ということです。パソコンやタブレットが手元にあることや、周りに見ている人がいない環境は、さまざまな「ながら」がしやすいものです。この「ながら」を避ける環境をつくって自分自身をコントロールし、学校にいるのと同じように授業に参加し、宿題にもしっかりと取り組む。対面であろうとオンラインであろうと、学校の授業を真剣に受けて、Z会もやって…と、24時間のうちの使える学習時間をしっかりと使うことが、学習効果を高めることにつながります。
―オンライン授業に変わっても、やるべきことは変わらないということでしょうか。
そうです。集中して授業を聞き、宿題にも真剣に取り組むという基本は変わりません。そのうえで、ICTを使うとさらに発展的に学びやすくなるでしょう。先ほど話したMOOCなどで世界中の大学の授業を受けるなどして、自分の興味・関心を深めていけるとよいと思います。MOOCの場合、映像のスピードを遅くしたり、字幕を表示できたりするので、辞書機能を使いながら学んでいる高校生はいますよ。留学するよりもハードルが低いですし、大学レベルの学習素材にアプローチすることで、将来やりたいことや学びたいことを考える機会にもなるので、ぜひチャレンジしてほしいですね。
ICTを使って学び続ける
―私たちが今後ICTを活用しながら学び続けるために必要な力は、どのように身につけていけばよいのでしょうか。
それには、3つの段階があります。第1段階は、ICTを学習の道具としてちゃんと使えることです。みなさんは、パソコンやタブレットを使って「レポートのような長い文章を入力し、きちんと推敲する」「Webサイトから必要な情報を探す」「計算式を入れた表をつくる」といったことはできますか? 大学生や社会人になればできてあたりまえと考えられていることですが、中高生にはこれまであまり求められてきませんでした。今回、オンライン授業をうまく活用できた学校というのは、コロナ禍以前からICTを使って学ぶことを取り入れていた学校です。いざオンラインでの学習が主流になったときに、使い方を知っていると、それだけスムーズに移行できるわけです。みなさんも、これを契機に、ICTを使えるようになってほしいですね。
第2段階は、オンライン上にある学習素材を自ら探しに行き、どんどん学習していくこと。Z会が提供しているICTを使った学習なども含めて、自分の理解度や興味・関心に合った教材・ツールを選んで積極的にデジタルで学習しましょう。「学ぶ」ということは、大学生になっても社会人になっても一生続きます。自分に必要な学習素材を自ら選択し、学ぶというくせを、今からつけておくとよいと思います。
第3段階は、人と知り合うことです。知識や技能を習得していくとき、その方法を一人で考えることはほとんどありません。多くの場合、「あの人のようになりたい」というモデルがいて、学び方や学ぶ道筋を模倣していきますし、それが知識や技能を得る近道でもあります。そう考えると、自分にとってのモデルになるような人と知り合うことがとても大事なことがわかると思います。そのための道具としても、ICTを使っていけるとよいと思います。
―オンラインで人と知り合うのはなかなか難しそうです。
たとえば、MOOCの掲示板には、共通のテーマ・分野に関心をもつ人たちが集まり、質問や議論をして学び合っています。そこからできたコミュニティや、そのほかの共通の興味・関心をもった人たちがSNSでグループをつくるなどしているので、保護者の方と相談しながら安全かどうか見極めて参加していくといいと思います。あるいは、保護者の方や学校の先生など上手に学んでいる大人がいると思うので、紹介してもらうのも一つの手です。こういった場で、「この子、中学生/高校生なのにおもしろいな」と大人に思わせてみましょう。喜んでいろいろと教えてくれますよ。
オンラインでなくても、「人に聞く」という力は大切です。自分だけで調べるのは難しいなと思ったら、先生や保護者の方に、「○○について、何か知っていますか?」と遠慮せずに聞く。これまでも、わからないことがあれば図書館へ行って本で調べたり、先生や周りの大人に聞くということは自然にやってきたと思います。それがICTを使うことで、本に加えてインターネットでも調べられるようになったり、身近な人以外にも知らないことを聞ける大人が増えたりするわけです。人が学んでいくということは、対面であろうとオンラインであろうと、本質的に変わるわけではありません。中高生を始め多くの学習者は、コロナ禍で、オンライン学習の海に突然投げ込まれ、右往左往してしまっている状態でした。でも、ちょっと落ち着いて、少しずつ新しい道具の使い方に慣れていけばいいのです。
むしろ、今後学び方以上に変化していくのは、学ぶ内容でしょう。今、プログラミングを学ぶ重要性や、問題解決型の学習の必要性が言われているように、時代の変化に即して必要な学習内容は変わっていきます。おそらく10年後はまた新しいことを学ぶ必要が出てくるでしょう。そこでも慌てることなく、変わらず学び続けられるよう、知識を得て活用していく力をつける、論理的に考える、人とコミュニケーションをとって思考を深めていくという基本を大事に学んでいってください。