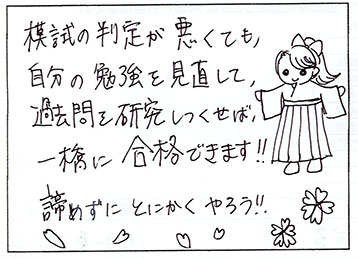合格体験記
模試の効果的な使い方と苦手克服のコツ
そろそろ模擬試験を体験する時期でしょうか。学校での団体受験や個人で申し込むなど、きっかけはいろいろだと思います。受験結果に一喜一憂するのではなく、その後の復習が重要であることは間違いありません。
憧れの大学に入った先輩方の模試活用法について紹介します。
解答冊子を最大限活用しよう!
模試は復習が一番大切です。しかし私は、模試を受けた後に判定結果だけを見て終わりにしてしまうことが何度もありました。そこで、「自分の答案のページを確認して全ての復習をし終えるまで、成績のページは見ない!」というマイルールを決めました。これにより復習する癖がつきました。復習時には解答冊子を熟読しました。中でも社会科目の解説は出題部分の周辺知識まで得ることができるため、自身の正誤に関係なくすべて熟読しました。そして、新たに得た知識やまた間違えそうだと思った知識事項を簡潔なQ&A形式にしてノートに書き留めていきました。社会科目についてはそのノートをすきま時間に繰り返し参照することで知識の抜けを埋めていくことができました。
準備と復習の習慣化
私にとって模試は受験勉強のペースメーカーで、弱点克服のためのツールでした。長期に渡る受験勉強では、どう学習計画を立てれば良いのか悩むこともあると思います。私は模試を学習スケジュールに組み込み「次の模試までに問題集をここまで解く」と決め、実行しました。模試で自分の学力レベルを把握することは重要ですが、模試受験の最大の目的は自分の弱点を見つけ、入試で同じ間違いをしないようにすること。模試後、すぐに答え合わせをし、間違った問題とその原因をノートにまとめていました。間違った問題を数ヶ月おきに解き直し、次の模試や入試に備えていました。成績が伸び悩む時期もありましたが、粘り強くこれらの習慣を続けました。
弱点を把握して改善する工夫を
模試は自分の弱点を把握し改善するのに最適なツールです。模試を何回か受けていくうちに、自分が緊張している時や焦っている時に忘れがち・見落としがちな点、犯しやすいミスの傾向が徐々に見えてくるはずです。私は間違えた問題をノートにまとめてはいましたが、解答解説を写したり事実を羅列した程度だったため、模試で問題を解くことに没頭していたり普段と違う緊張感が漂う中ではそこまで意識が行かず、なかなか模試でのミスが減りませんでした。なんとか改善しようと色々試して見つけた解決策は、試験中常に意識していたい事柄を「自分の言葉で」ノートにまとめる、というものでした。自分なりの言葉や表現に直して書き出したり声に出したりすることでより鮮明に頭に残り、試験中でも思い出しやすくなったのだと思います。
- 模試は、どこを学習すべきかが一番コンパクトにまとめられた最上の問題集です。なので私は、模試の復習だけは絶対に欠かさず、丁寧にやるようにしていました。数学だと、できなかった問題を左側に貼り、右側には解答を書く、英語だと不安な文法問題をまとめる、など教科により工夫しました。そして、これらを何度も繰り返し解き直すことで、定着させました。模試の復習ファイルは私の宝物です! (一橋大学・社会学部 はまちゃん先輩)
- 大切なことは、自分で工夫すること!模試の結果で一喜一憂するだけではなく、何がダメだったのか、改善策などを考えましょう! (早稲田大学・教育学部 ハリ太郎先輩)
- 模試は自分の到達度を図る材料として捉えましょう。間違えた問題については特に、どこをどうして間違えたのか、正解できるようにするにはどんな学習を追加すればよいのかを考えることが、実力アップへの近道です。 (京都大学・文学部 Y先輩)
- Z会は自分で進めるものなので、間違えた問題に対して自分の間違う傾向を考えるきっかけになりました。それが苦手克服につながったと思います。 (慶應義塾大学・法学部 K先輩)
- 英語は苦手で、単語・文法も全く覚えておらず、長文を読む時に構文をとることが全くできませんでした。しかし、Z会の映像で単語の覚え方や、構文のとり方、英語の勉強の仕方について学び、それを実践することで、英語の苦手意識がうすれていきました。 (千葉大学・工学部 皿先輩)
- 苦手教科は夏までにそこそこの点数を取れるまで上げておき、夏以降は理科の対策に集中できるようにしました。 (京都大学・工学部 Y.Y先輩)