これまであなたが学んできた「学びの成果」はどうやって振り返っていますか? ノート、テストや「添削問題」をとっておくというのも、一つの方法でしょう。東京学芸大学の森本康彦先生は、自分の学びを振り返る方法として「ポートフォリオ」を上手に使うことを提唱されています。これまでの学びをこの先の学びに生かす「ポートフォリオの使い方」をうかがいました。
自分の学びを振り返る「ポートフォリオ」の使い方
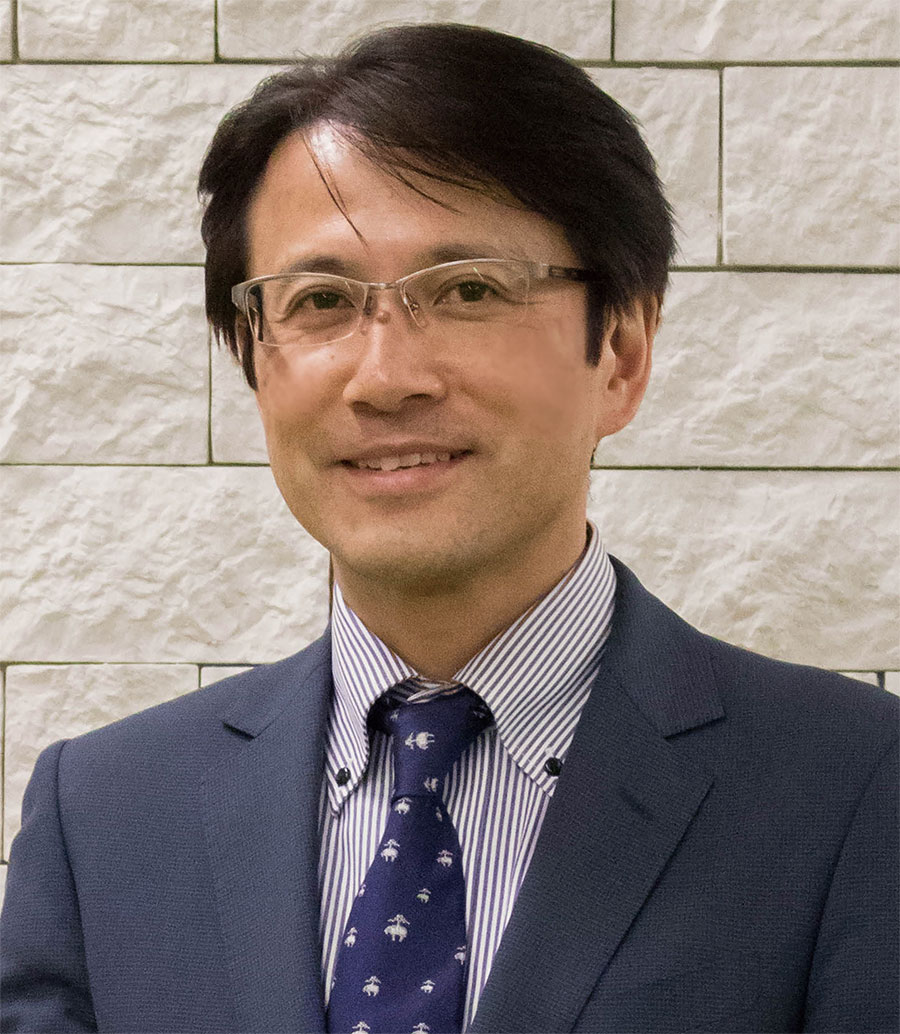
森本 康彦先生
(東京学芸大学 ICTセンター 教授)
博士(工学)。1991年学習院大学理学部数学科卒業後、企業の情報技術研究所にてソフトウェアの開発に従事。その後、1996年から中学校(数学)、高校(情報)の教鞭をとる。2007年、長岡技術科学大学大学院工学研究科後期博士課程修了。2009年、東京学芸大学情報処理センター准教授に。2017年より現職。教員や児童、学生を対象に、ICTを使った学び方を紹介する講演やセミナーも多数実施している。
「ポートフォリオ」という言葉を聞いたことがありますか?それは、みなさんが学んだことや成果を記録として残したもののことです。たとえば、授業のノートやプリント、テストだけでなく、そのときにひらめいたメモや友達からのコメント、先生からのアドバイスも一緒にとっておけば、それらすべてがポートフォリオと言えます。そのほかにも、学校行事や委員会活動などの取組の状況や成果を記録したもの、資格や検定も取得した賞状だけでなく、取得するために努力した記録も含めてポートフォリオです。また、部活動の練習や試合後に自ら振り返って書き込む「部活ノート」はポートフォリオそのものです。つまり、ポートフォリオは、自分の学びの成果がぎゅっとつまったものですが、それを見返すと自分が学び成長したことが手 に取るようにわかるようになります。
しかし、このポートフォリオを自分の「学びの記録」や「学びの振り返り」、そして「今後の目標を立てる」ためにきちんと利用できているでしょうか? 本来、ポートフォリオは、自分の学びをもっとよくするために使うものなのです。そこで、みなさんに「学びのポートフォリオ」を使った効果的な学習法についてお話ししたいと思います。
振り返りながら学ぶ、「リフレクティブ・ラーニング」
私や、みなさんのお父さんやお母さんが中高生のころは、「知識を蓄える」という学び方が主流でした。いわゆる「暗記」をすることが学習の主体だったのです。テストでは、習ったことをきちんと覚えているかということが問われるので、必死で教科書やノートの内容を頭に叩き込みました。
みなさんの学習でも、知識を蓄えることはもちろん大切なのですが、蓄えるに至るプロセスが違います。ただやみくもに教科書の内容や先生の板書を覚えるのではなく、なぜそうなるのかを自分で考え、さらに友達の意見や先生の説明を聞きながら納得して理解することで、自然と自分の知識としていく…というような学び方をしているのではないでしょうか。
たとえば、先生の説明を聞いて、「なるほど。自分で考えたのとは、ちょっと違うな」「今の方法でやってみよう」「できた、できた。じゃあ次の問題でも同じようにやってみよう」というように、学習しながら知識を自ら構築していくというような姿勢はとても大切です。
学習の例ではピンとこないかもしれませんが、同じようなことは部活動でよくやっているのではないでしょうか。練習中はたくさんの失敗をしますよね。でも、その失敗を成功につなげるために、自分で「こうしたほうがいいのかな?」と気づいたこと、仲間やコーチに指摘されたことを一つひとつ実践してみているのではないでしょうか。しかも、その一回一回の練習は独立しているのではなく、昨日やったことがきちんと今日に生かされているか、今日新たに出てきた問題点を次回の練習ではどのように改善していこうか、そして本番の大会のときにはどうなっていたいのか、というように、1週間、1カ月、もしくは1年という長期的な見通しを立て、毎回の練習を振り返りながら粘り強く練習していって次につなげていく…というのをみなさんやっていると思うのです。
この「振り返りながらたくさんのことに気づきながら学ぶ」ということは、「リフレクティブ・ラーニング」とも呼ばれているのですが、私たちは、「ああ、だから間違っていたのか」「彼はどうやっているんだろう。ちょっとまねしてみようか」というように、日々“気づきながら学んでいる”ます。この、「いろいろなことに気づき、自問自答をしながら、トライ&エラーを繰り返すことで問題を解決していく」学び方がとても大切なんです。
「気づきながら学ぶ」とは
「気づきながら学ぶ」という姿勢は、部活でも学習の場でも同じように必要だったように、中高生のときだけでなく、大学生になって研究を進めるようなときにも、社会人になって会社で働くときにも必要です。ですので、早いうちにこのように学ぶくせを身につけておきたいものです。
最初のうちは、慣れていないでしょうから、次の四つの視点を意識してみてはいかがでしょうか。一つ目は、「見る」気づき。教科書を見たり、教材を見たり、人がやっているのを見たり、自分がやっているところのビデオを見たり、何かを見ることで得る気づきです。問題集の模範解答を見て、ただ写すというのが勉強にならないというのは、わかりますよね。解答を見て、「ああ、ここが間違っていたんだ。こうやればよかったんだ」と気づいていきます。
二つ目は「かく」気づきです。自分で解答をノートに書いているときに気づくこともあるし、絵を描いたり図に描いたりすることで気づくこともありますね。自分が書くことによって、「こうすると、こうなるはずなんだけど…」「また同じ間違いをしてる。だったらこうすればいいのか」というように、かきながら、考えているわけです。
三つ目は、「選ぶ」気づき。「このやり方だ」と自分で判断して選ぶことです。見たり、かいたりして学びが進んでいくわけですが、その途中では必ず、「このやり方がいいはずだ」「いや、こっちがいいよな」と自分で判断して学びの方向を調整します。この「判断」がとても大切で、そこにはたくさんの気づきがあります。私たちは、見て、かいて、判断して選ぶ。これを繰り返しながら、「できる」ようになっていくわけです。
そして、最後の四つ目ですが、「話す」気づきです。問題を解いている横で、先生が「ちょっと違うかな」と言っただけで、少し考え直して「あ、わかった」となる友達の姿や、グループで一緒の問題を解いているときに、「ああでもない、こうでもない」とわいわい話しながらやっていると、「あ、わかった!」という人が説明を始めたとたんに、自分も一気に答えが導き出せたということがあるでしょう。実は、ほかの人と話して学び合うという経験は、とても学習効果が高いということがわかっています。
それは、学ぶということは「気づくこと」だからです。人と話すほかにも、自分との対話「自問自答」でも、同じように効果があります。勉強をしながら、「ここは前にも同じような間違いをしたから注意しないといけないな」「よし、わかったぞ。じゃあ、もう一度やってみよう」と、自分の中で自問自答しながら学習を進めることはみなさんにも経験があると思います。自問自答をするというのは、“振り返り”をしている、ということです。話すことで、自分の頭が整理されるので、そこから新たな気づきが生まれていくのです。
「気づき」を見える化する学びのポートフォリオ
ですが、日々学ぶなかで生まれるこうした「気づき」をみなさんはどうしていますか? 何もせず、そのままにしていることが多いのではないでしょうか。気づくことが学びであるのならば、気づきをそのままにしているのは、非常にもったいない。「同じような問題で引っかかる」「このパターンはこの公式を使えばいい」、問題を解いていて気づいたことは、一緒にノートに書いておき、それをいつでも振り返ることができるようにしておきましょう。
今までだって、授業中に「ここは大事だな」と思ったところや、後でもう一回解き直してみようと思ったところは、ノートの端にちょっと書いておいたり、付箋を貼ったりしていましたよね。そんな感覚で、自分の気づきを「ちょっと書いて」おくのです。
ただ、ノートには少し残念なところもあります。それは、いつでもどこでもたくさんのノートをいっぺんに持ち歩くことができない、という点です。「あのときはどうやって説いたのかな?」と一年前のノートを学校で見返す…というのは、なかなか難しいでしょう。勉強をがんばればがんばるほどノートは増えていきますから、それを全部いつでもどこでも見直しができるようにするというのは不可能です。
しかし、それをクラウド上に蓄積していったらどうでしょう。スマートフォンで撮った写真をクラウドに上げておけば、1カ月前どころか1年3年前の写真だってパソコンやスマートフォンから簡単に見ることができますよね。同じように、自分のこれまでの学びの過程がクラウドに置いてあれば、気になるときにいつでもどこでも、自分でアクセスすることができます。これまでやった学習のノートを見ながら、今の学習に生かすことも容易にできます。そして、それはそのままこれまでの学びの過程を振り返ることのできる「学びのポートフォリオ」になるのです。
自分の学びを記録するポートフォリオの作り方
では、どのようにこのポートフォリオを作っていけばよいのでしょうか。
やはり簡単なのは、タブレットやスマートフォンを使うことです。タブレットやスマートフォンのカメラ機能を使ってノートやテストを記録していきましょう。
最初のうちは、何を写真に撮ればいいのか迷うかもしれませんね。であれば、ノートの写真を撮ってためていくことから始めましょう。単元の学習が終わったときのような、切りのよいところまで写真がたまったら、今度は残しておく写真を選ぶ作業に入ります。全部の写真をとっておくのではなく、その単元の大事なところをまとめたダイジェスト版にするのです。すると、ノートの大事なところだけをまとめた「まとめ写真集」ができあがります。まとめができあがったら、そのまとめを見て気づいたことをメモしておきましょう。端末の中にあるメモ機能を使ってもよいですし、それこそノートに書いて写真に撮って、最後のページにくっつけておけばいいのです。
ポートフォリオを作成するなかで、一番大事なのはこの写真の選別をしながらまとめる作業です。「このページは絶対に残しておかなくてはいけないぞ」「このページは要らない。ここだけアップして撮っておこう」というように、写真を「振り返り」ながら選びます。ノートをまとめてさらにそのノートをまとめるというプロセスが復習になり、さらに自分の思考の整理につながるのです。
もう少し慣れたら、やみくもに写真を撮るのではなく、テーマを決めて、ポートフォリオの中にフォルダを設定してみましょう。たとえば、「テストの復習」ではどうでしょうか。
返ってきたテストを写真に撮る。そして、テスト直しをノートにする。そのテスト直しのときには、問題を解き直すだけではなく、そのとき気づいたことも一緒にメモをしておきましょう。そして、できたテスト直しのノートを写真に撮ります。それをテストのたびに行っていくと、かなりの数のテストとテスト直しのノートの写真がたまっていきますね。たまった写真をパラパラと見ていくと、「同じようなケアレスミスをやっているな」「1年生のときにはこんなことがわからなかったのか」「これは、今はもうちゃんとわかるようになったな」など、新たな気づきが生まれるでしょう。こうやって機会があるごとに「振り返り」をすることを習慣づけていくのです。
このまとめ方は、千差万別。人によって人の数だけまとめ方があると思います。テスト前につくるまとめノートだけをまとめたフォルダを作る人もいるでしょうし、ノートの端に書いてある気づいたところだけをピックアップして写真を撮って「気づきフォルダ」を作る人もいるでしょう。どんなフォルダにまとめていこうかな、と考えることも、学びの一つの過程です。「自分にとってはこれを一連にまとめておくことが大事だな」と気づくこと、そしてそれをかたちに残す作業ができる力も大切だからです。
もうお気づきだと思いますが、写真を撮ってためるだけではポートフォリオの意味はありません。「書いて」「まとめて」それを「見返す」ことが大事なのであって、私がスマホやタブレットをすすめるのも、そのほうが見返しやすいからです。ICTを使ったポートフォリオだからいいというわけではなく、デジタルを使うのは、ただの手段。これを使うとラクに進めることができるから、学習用の文房具の一つとして取り入れることをおすすめしているのです。
ポートフォリオは学びの「ネタ帳」
このポートフォリオを使った学習では、「ノートを見る」「ノートを見て気づいたことを書く」「撮った写真の中から残す写真を選ぶ」という「見る」「書く」「選ぶ」の三つの気づきまでを自分で行うことができます。次に、「それを見て友達と教えあう」という四つ目の「話す」気づきも取り入れてほしいと思います。同じ単元のまとめノートを見ながら話していても、「大事だと思ったところが違うんだな」「あのまとめ方の方がわかりやすいな」「ん? 彼がわかったと思っているのはちょっと違うんじゃないか?」など、また新たな気づきが生まれてくるはずです。
ポートフォリオはいわば自分の「ネタ帳」みたいなものです。芸能人やお笑い芸人にとって一番大切なあのネタ帳です。自分の得意なネタ、苦手なネタのすべてがこのネタ帳の中に入っているわけです。ですから、学習のなかでうまくいったことも、失敗してしまったこともすべて端末の中に記録しておきましょう。
すると自分の成長が簡単に振り返りやすくなります。ネタのタイトルを見たら「最初はすべってばかりいたネタだったのに、改善を繰り返したらウケるようになったなぁ」とすぐに思い出せるように、写真をパラパラ眺めるだけで、「最初は苦手だったのに、公式をきちんと理解したからもう間違えることはないな」と自分の成長を簡単に振り返ることができるようになりますよ。そして、たくさん写真がたまればたまるほど、「できない」ことがどれだけ「できる」ようになったのか、自分がどれだけ進歩したのかがよくわかるでしょう。
そして、ポートフォリオは自分だけのネタ帳ですから、ほかの人のネタ帳と比べる必要はありません。何を大事だと思い、何を記録しようかと判断するのは、人それぞれ違うのはあたりまえですから、同じものが作れるはずはありません。写真の枚数の多い少ないも関係ありません。ですが、おたがいのネタ帳を友達どうしで共有して、議論をすることは大切です。ポートフォリオを見ながら話を深めることで、自分のネタ帳をもっともっと深めることができるのです。
自分の考えたことを言葉に表現して、それをさらに振り返る。それを友達と話すことで次の考えにつなげていく。そして、改善点があればそれを見つけて修正していく――。振り返りながら学ぶ=リフレクティブ・ラーニングを、ポートフォリオを介してぐるぐると行っていくと、自分なりのポートフォリオの作り方がだんだん定まってくると思います。すなわちそれは、あなたならではの「学習法」です。自分にあった学習法で学ぶということ自体が学びを進めるうえでの大事な力の一つです。ポートフォリオを試行錯誤しながら作ることで、あなたに必要な学びの姿が見えてくると思います。
電子的に記録したポートフォリオ=「eポートフォリオ」
これまで説明してきたように、タブレットやスマートフォンなどのICTでクラウド上に保存したポートフォリオは、時間的・空間的制約を取り除いてくれ、いつでもどこでも、どんなに月日がたってもアクセスできるので、自由に学びに利活用できてとても便利です。この電子的に記録したボートフォリオを「eポートフォリオ」と呼んでいます。
ここで説明した学習法をeポートフォリオで実行していくことで、あなたは、自身の学びの主人公となり、成長し続ける「アクティブ・ラーナー」として羽ばたいていけるでしょう。
バックナンバー

