このコーナーでは、中高生の日々の生活で見られる問題や悩みを取り上げ、仲間を引っ張る立場として、どのように対応すべきかを紹介します。
リーダーのための
コミュニケーションスタディ
みんなの行動を引き出す コミュニケーション
中学2年生のサエは、新しいクラスになった翌日の係決めで、「教材係」をすることになりました。係のメンバーは4人でリオ以外の3人は、中1のときも同じクラスで気心が知れています。係が決まった後、「それぞれで係の仕事の確認をして、今後の計画を立てて、質問があれば聞きにくるように」と担任の先生から指示が出て、その後は係ごとの話し合いが始まりましたが、リオを含めた4人で係活動を行うことに不安を感じ、みなで協力したいと思っています。
参考図書『自分らしく生きるための人間関係講座』(大和書房)

シーン① 自分たちのやることを共有する

あっ、ごめんね。リオさんに押しつけるつもりはなかったんだけどさ。係の仕事がよくわかっていなくて。何をやればいいのかな?
そうか、仕事の内容がよくわからないから判断できないってことだね。本当だね。
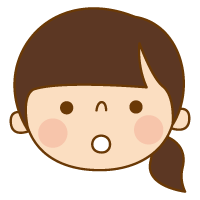

このプリントに仕事内容「教科の教材や資料などの準備」って書いてあるけど、各教科ごとに違うしね。1年のときと同じ先生は授業のやり方がわかるけど。
教科ごとの準備内容が違うこともあるよね、確かに。
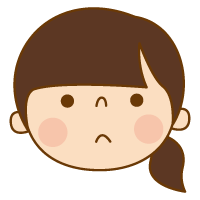

このプリントに書いてある内容じゃ、来週の授業で早速何をすればいいのかがわからないね。
そうそう。これって各教科の先生に聞いた方がいいんじゃないの?
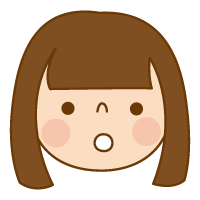
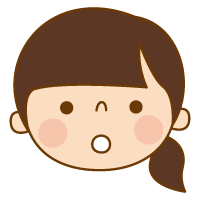
なるほどね。直接、先生に聞けばわかるんじゃないかってことだね?
でもさ、いつ、聞くの? 部活の顧問の先生とかは、なかなかつかまらないよ。朝練、昼練、夕練のあるクラブもあるし、昼間は授業だしさ。

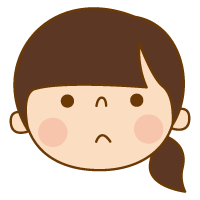
そうか、先生に聞くタイミングがなかなかないのか。どうしたらいいんだろうね。何かいいやり方はないかな?
シーン② 係の仕事の仕方について意見を出し合う
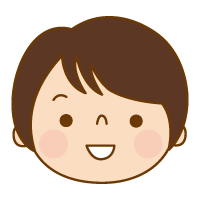
それぞれの先生の机の上に、「次の時間に、教科で用意するものなどがあったら以下に書いてください。2年3組教材係」って書き込み用紙を置いておいたら?
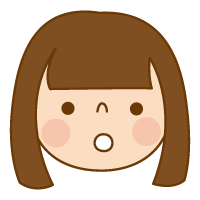
「いつまでにお願いします」も書いておいて後で回収に行くのは? それなら、部活の合間に取りに行けるよ。
いいと思う! 授業が始まってからは、授業の最後に「次の授業で準備するものがあれば教えてください」って聞けばいいよね?
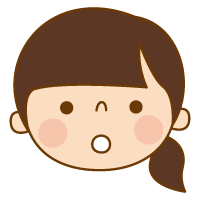

だよね! 名案じゃない? それで、教科を4人で分担すればいいんじゃないかな。重い物とかあれば4人で運んだり、男子に頼んだりするのもありだと思う。
いろいろアイデアが出たね! OK、それじゃ、これまで出た意見を書いていくね。
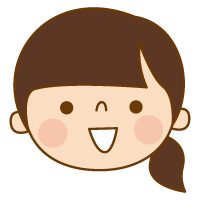
シーン③ 話し合いの内容をまとめる
全員の意見が出たところで、サエはみんなの案をまとめていきました。係の仕事の「何を、どのようにする」のかの部分が明確になっていきました。
1) まず、教科ごとに必要なものを担当の先生に聞くための書き込み用紙を作り、机の上に置くか、直接渡す
2) 仕事の内容はおそらくプリント配布、授業で使う機材の準備、宿題やレポートの回収など
3) 2回目の授業からは、次回の授業の準備などを直接先生に確認する
4) 1)の作業は毎回しなくてよくて、長期休み前や、休み明けなどに行う
5) このように各教科の先生に直接聞いてもいいのかを、担任の先生に確認する
6) 4人全員でやるが、教科ごとの担当を4人の中で一応決める
7) 担当者の決め方もみんなで話し合う
8) 誰かが欠席する場合もあるので、担当者以外に、サブ担当者も決める
9) やってみて不都合があったら、すぐにみんなに相談する
今回のポイント
その後担任の先生の許可を得て、実際に各教科の先生に書き込み用紙に記入してもらったところ、積極的に自分たちから行動したことを多くの先生がほめてくれました。ほかのクラスの教材係は、一時間目の授業のときに、仕事内容を教える形だったので、生徒の側からアクションを起こしたのは想定外だったと言われました。
この話し合いをしたことで、4人全員が教材係の仕事についてしっかり考えたので、全員が積極的に取り組むことになりました。リオはすっかり、ほかの3人と打ち解けて、自由に意見を言うようになりました。
そして、グループが話し合いをしながら、それぞれの「存在」や「思い」や「考え」を尊重して、全員納得のできるやり方を見つけていくことができたこともすばらしいですね。
実は、話し合いの間のサエの会話に秘訣があります。
- 相手の話を否定せずに、まずは相手の言っていることを理解する意識をもつ。
- 自分の理解したことが間違っていないかを確認する。
- 必要なときには、自分の意見も明確に自己表現をする。
- 「どうしたらいいかな」と全員で考えるチャンスをつくる。
- 出てきた案は全員の合意のうえで、それを試す。
- 案を出すときには、一切評価をしない。
など、このようにサエが会話の中で気をつけたことによって、全員のやる気や考える力を引き出すことができました。
さて、この話し合いの前日に行われた自己紹介の様子も見てみましょう。

文:今井 真理子
(暮らしとコミュニケーション研究所代表・親業訓練協会シニアインストラクター)
http://www.happy-communications.com


