宿題、部活、課外活動など、日々忙しく過ごしていると、つい疎かにしてしまいがちな「睡眠」。でも、睡眠時間を削ったり、不規則な生活をしたりすると、思うように勉強が進まなかったり、体が重く感じたりすることも多いと思います。自分にとって快適な睡眠時間を知り、生活リズムを整えるには、どうすればいいのでしょうか? 広島大学で睡眠に関する研究に取り組まれている林光緒先生に、睡眠の重要性や、夏休みにできる最適な睡眠時間を見つける方法などを伺いました。
成績を上げたいなら、8時間寝よう!
~夏休みに試せる! 自分に「最適な睡眠」を見つける方法~
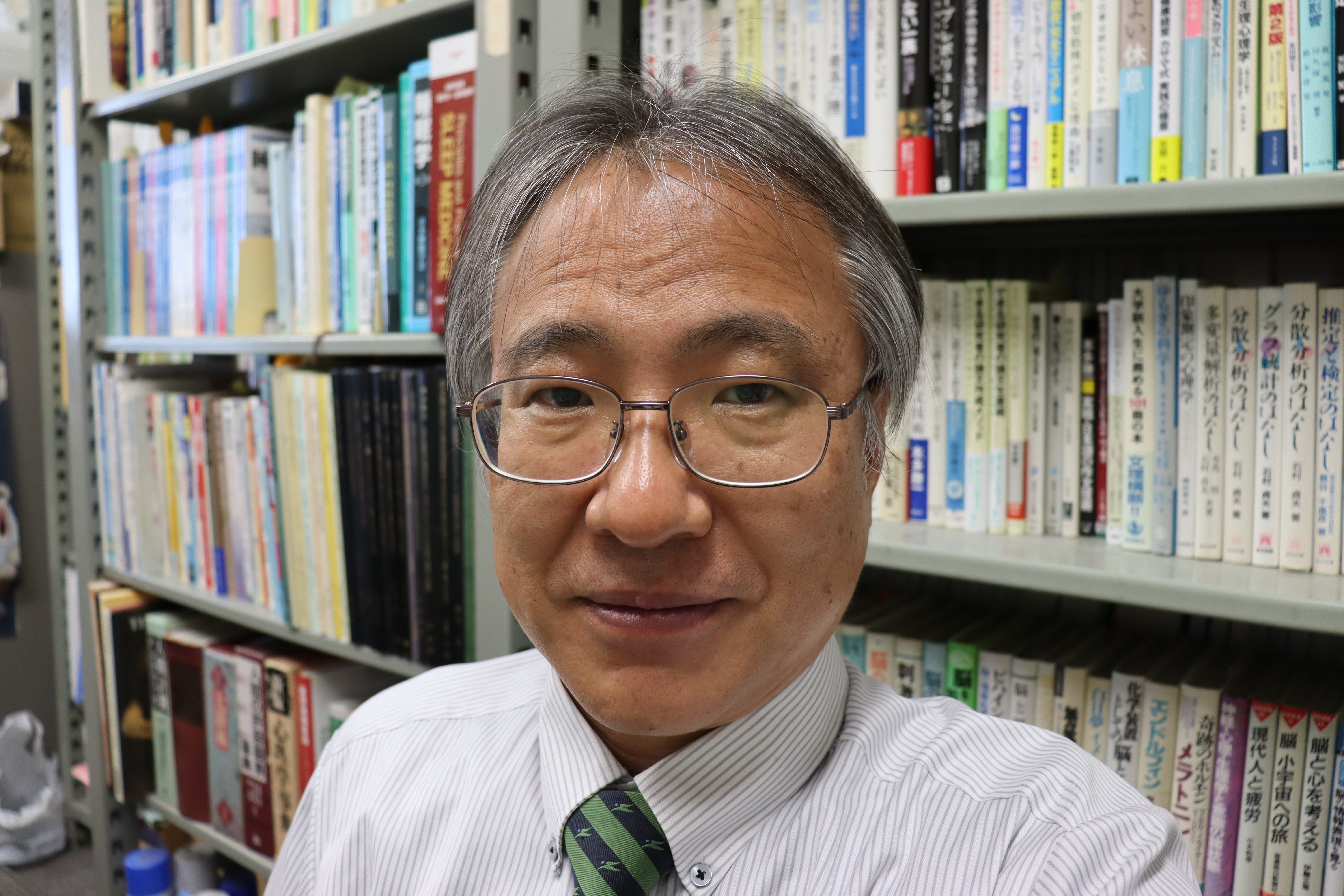
林光緒先生
(広島大学大学院人間社会科学研究科 教授)
1962年三重県に生まれる。1991年広島大学大学院生物圏科学研究科博士課程修了。現在、広島大学大学院人間社会科学研究科教授。学術博士。著書に『睡眠心理学』(共著 北大路書房)『眠気の科学』(編共著 朝倉書店)などがある。
睡眠時間を削って勉強しても成績は伸びない!?
――日々忙しい最近の中高生は、常に睡眠不足の状態にある生徒が多いと言われます。では、睡眠不足にはどのような問題があるのでしょうか?
中高生にとって、なぜ睡眠不足がよくないのかと言うと、“しっかり寝ないと成績が上がらない”からです。記憶というのは睡眠中に定着していくものなので、いくら勉強しても、睡眠そのものの時間を削ってしまうと、せっかく勉強したことが記憶として定着しません。「寝る間を惜しんで勉強する」なんていうのは、間違った方法です。
というのも、睡眠中は一日フル活動していた大脳が唯一休める時間ですから、その時間に、脳の機能を回復する役割を負っています。ですので、睡眠時間を削ると脳の機能が回復せず、記憶が定着しないだけでなく、感情のコントロールも悪くなり、キレやすくなったり、我慢できなくなったりします。また、免疫や代謝にも影響して、疲れやすくなったり、眠気が起こったり、運動パフォーマンスが低下したりもします。
このように、睡眠時間を削った結果には、ネガティブな効果しかなく、ポジティブな効果は一つもありません。
――では、どのくらい睡眠時間をとったらいいのでしょう?
「パフォーマンスを上げるために必要な睡眠時間は1日8時間以上」と考えられています。
この8時間という数字は、アメリカの国立睡眠財団(National Sleep Foundation)が行った調査結果に基づきます。調査によると、14歳〜17歳に推奨される睡眠時間は「8〜10時間」とのこと。8時間を切ると、睡眠不足が影響して心身のパフォーマンスが落ちることがわかっています。
ただ、これだけの睡眠時間をとろうとすると、勉強する時間が不足してしまうという不安を抱く人もいるでしょう。それなら、それを逆手にとって、集中して勉強することを考えてみましょう。私がこれまで見てきた成績のよい人たちというのは、睡眠時間を十分にとり、勉強する時間には集中して勉強する、また、夜にしっかり寝ているので昼間に眠くなることがなく、授業中に聞いたことはおおむねその場で頭に入れられる、という共通点があるからです。睡眠時間を1時間でも2時間でも伸ばすことで日中の覚醒レベルは変わってきます。そうすると理解のできる量・質もおのずと変わってきます。
睡眠不足を解消する、「最適な睡眠時間」の見つけ方
――毎日8時間も睡眠時間をとれないが、今の睡眠時間でちょうどよいと考えている人もいるかと思います。そもそも「自分が睡眠不足かどうか」はどのようにして判断するのでしょうか?
朝、アラームをかけずに、人にも起こされることなく、自分の力だけですっと目が覚めるかどうか。これができなければ睡眠不足ですし、できるなら睡眠不足ではありません。
ちょうど、夏休みの時期ですから、「自分にとって最適な睡眠時間」を探ってみることをおすすめします。具体的には、毎日たっぷりと寝ることを2週間くらい続けてみましょう。すると、徐々に自分にとって最適な睡眠時間がわかってきます。
実際、被験者の方に1日10時間以上の睡眠を1カ月間続けてもらうという実験がありました。みなさん、最初の1週間は9時間くらい眠れるのですが、眠れる時間はだんだんと減ってきて、2週間目になると長い人でも8時間半くらいしか眠れなくなるのです。それが、その人にとっての最適な睡眠時間ということになるのですが、そうやってまずはなるべくたくさん寝てみると、自然と自分にとってのベストの睡眠時間がわかってきます。
――この方法を試すときに注意すべきことはありますか?
3つあります。
1つめは、朝起きる時刻を固定すること。7時なら7時に固定して、その時刻に必ず起きるようにしましょう。平日、休日にかかわらず、毎日これを続けてください。これによって生体リズムが安定してきます。
2つめは、朝起きたら、窓の外を見て自然光をしっかりと目に入れること。自然光にはブルーライトが含まれていて、体内の24時間リズムをリセットするはたらきがあるのです。これによって生体リズムの安定化が強化されます。
3つめは、昼寝や夕寝はしないこと。30分以上の昼寝や夕寝をしてしまうと、睡眠が深くなりますが、その分、夜の深い睡眠が減ってしまいます。そのために、夜は早寝どころか、なかなか寝つけなくなってしまいます。15分程度の短い昼寝であれば、睡眠は深くなりませんので、夜の睡眠には影響はありませんし、眠気がとれ、活動的になれることがわかっています。しかし、昼寝は気持ちいいので、夏休み期間中はつい30分以上眠ってしまいがちですから、最初から昼寝や夕寝はしないよう心がけた方がよいでしょう。
これらに気をつけて、夜になるべく早く寝るようにすると、どの時刻に就寝すれば一番調子がいいかがだんだんとわかってきます。朝、アラームがなくてもすっきりと目が覚めて、日中、居眠りをすることなく元気に過ごせる就寝時刻と睡眠時間が、その人にとって最適なのです。
この方法を知っていれば、今後、どれだけ睡眠リズムが崩れても元に戻せます。だまされたと思って2週間続けてみてください。また、睡眠日誌として、「前日の就寝時刻」「起床時刻」「その日の状態」を記録していくと、より客観的に睡眠時間と体調との関係や、生活リズムの課題などにも気づくことができますよ。
――早く寝ようとしてもなかなか眠れないこともあると思います。どうすればすっと眠れるでしょうか?
自然と眠くなるために重要なポイントの1つが、「光」です。夜にブルーライトを浴びると、寝つきが悪くなって体内リズムがずれてしまうため、日没後の部屋の光は、ブルーライトを多く含む蛍光灯やLEDライトの全灯状態を避け、全灯ではない明るさに調光するか、白熱灯を利用しましょう。
また、パソコンやタブレット端末の明かりも、ブルーライトを含むので夜間の長時間使用は避けましょう。スマートフォンの明かりにもブルーライトが含まれますが、画面が小さいため影響はあまりないと言われています。ただし、就寝前にスマートフォンを見ていると脳が活性化するため、少なくとも就床30分前からは見ない方がよいでしょう。
「睡眠の質」「寝溜め」「昼寝」も誤解だらけ!?
――睡眠不足の解消方法として、「睡眠時間は短くても睡眠の質を高めることでなんとかしたい」と考えたくなりますが、それは可能なものでしょうか?
睡眠の質が高い状態というのは、「一度寝たら途中で目が覚めない」状態のこと。この状態にある時点で睡眠の質は最高になっているので、それでも睡眠不足を感じるなら、量が足りていないということです。
寝つきが悪い=睡眠の質が悪いと捉える人もいますが、それも誤解で、寝つきの悪さと睡眠の質は関係ありません。むしろ関係があるのは体温で、寝つきの悪さの一因である夜ふかしをすると、体温のリズムが崩れて寝つきが悪くなることが科学的にわかっています。
どういうことかというと、体温には、夕方に最高体温に、明け方に最低体温になるという24時間間隔のリズムがあります。そして、人間の体は、最高体温と最低体温のちょうど真ん中付近まで体温が下がると眠ることができ、さらに、最低体温から2時間ほど経つと目覚めるメカニズムになっています。
ところが、夜ふかしをすると、体温の高い状態が夜間まで続いて体温リズムが後ろにずれてしまうため、寝ようと思っても眠れなくなるのです。そのため、寝つきは悪いが一度眠ったら途中で目が覚めることはほとんどなく、朝はなかなか目が覚めず、日中も眠くてしかたない、ということが起こります。これは体温リズムの乱れによる「概日リズム障害」と呼ばれるもので、不眠症ではありません。寝つきが悪い=不眠症とは単純には言えないのです。
――「寝だめ」はどうでしょうか? 平日の睡眠時間を補うために休日に寝だめをする、という人もいますが…。
本来、睡眠はためられるものではありません。私たちが寝だめと呼んでいる行為は、睡眠をためているのではなく、日々の睡眠不足が積み重なった睡眠負債という借金を返済しているだけなのです。
そして、休日の寝だめで朝寝坊をすると、ますます体内のリズムを狂わせることになります。
――そうならないためにはどうすればいいでしょうか?
まずは、できるだけ借金をためないことです。平日に10分でも20分でも早めに寝て睡眠時間の不足分を減らしておく。そして、土日に不足分を解消する場合、2時間以上長く寝ないことです。
平日の睡眠時間を増やすのはなかなか難しいかもしれませんが、一度、睡眠にあてられるような無駄な時間がないか見直してみることをおすすめします。日本学校保健会の調査によると、睡眠不足を感じているという中高生にその理由を尋ねたところ、「なんとなく夜ふかししてしまう」が上位に入っています。心当たりのある人は、「なんとなく夜ふかし」の時間を削って、睡眠時間を増やしましょう。
――「昼寝」はどうでしょうか? 睡眠不足を補うものになりますか?
昼寝は、昼間の眠気をやり過ごす方法としては適していますが、睡眠不足を補えるものではありません。厳密に言うと、1時間くらい寝れば睡眠不足の解消になりますが、その分、夜の睡眠を妨害することになってしまうため、長時間の昼寝はすべきでないと考えます。
――では、どういう昼寝ならよいのでしょうか?
先に述べましたように、中高生の場合、10〜20分くらいの昼寝が昼下がりの眠気解消につながります。夜の睡眠をたっぷりととっていても、昼下がりに眠くなることは、人間の体のリズムとしてあるものですから、その解消方法として昼寝をするというのは有効な方法です。
昼寝の時間は、短すぎても効果がなく、最低10分は寝ないと効果がないことが研究でわかっています。というのは、昼寝は、寝始めてから5〜6分間はうとうとした状態が続き(ノンレム睡眠の睡眠段階1)、その後、意識が飛んで体の力が抜け、軽い眠りの段階に入ります(ノンレム睡眠の睡眠段階2)。この段階が3分以上続く、すなわち、10分ほど眠れば、記憶や運動パフォーマンスが上がるのです。
睡眠段階2は体の力が抜け、頭が支えられなくなりますので、頭をどこかにつけることが有効です。机にうつ伏せになる、壁に寄りかかるといった姿勢で眠るとよいでしょう。机にうつ伏せになって寝ると腰が痛くなる人は、いすと机の高さが合っていないので、机の上に教科書などを置いて頭の位置を高くし、背中をあまり曲げない姿勢で寝るようにするとよいでしょう。
よい”睡眠習慣”で心身ともに健康になろう
――睡眠の習慣をつける大切さがわかりました。中学・高校時代の生活に限らず、長期的に見ても、睡眠の習慣というのは大事でしょうか?
中学・高校は始業時刻が毎日決まっていますが、日によって授業開始時間が異なる大学生は、そのために生活が乱れる人が多いようです。睡眠を十分にとる習慣がなかったり、睡眠リズムを戻す方法を知らなかったりするために、朝起きられない→午前中の授業に出られないか、出られても午後の授業が眠くて頭に入らない→単位がとれず留年を重ね、退学せざるをえなくなる、という悪循環を起こす学生は実際にいます。みなさんには、そのようなことになってほしくありません。
また、メタボリックシンドロームや心疾患などは、睡眠不足とも関係があることがわかってきています。この点で、睡眠は将来の健康維持のためにも重要です。
そのためにも、ぜひみなさんには、心身ともに健康に過ごせるよう、今のうちから睡眠のメカニズムを知り、睡眠を十分にとる習慣をつけてほしいと思います。
――ありがとうございました。

