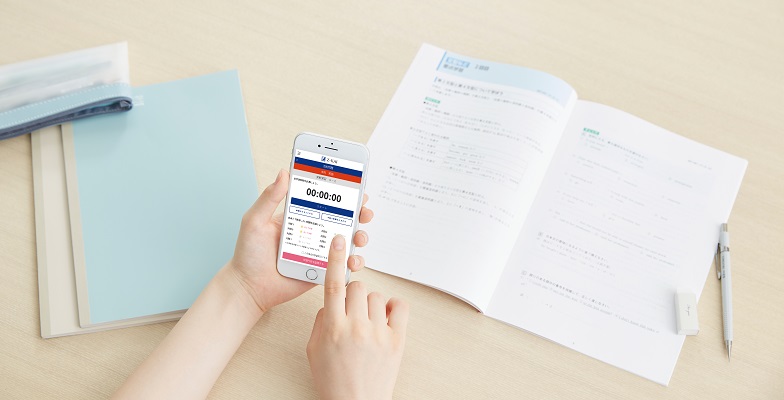
学習記録をつけるだけで、楽しく勉強が続けられる!?
廣瀬さんは大学在学中に起業して、学習内容を記録・可視化するサービス「Studyplus」をリリースされました。そもそも、そのアイデアはどこから生まれたのでしょうか。
高校時代、バスケットボール部の先輩に、高3の夏まで部活を続けたうえ、東大に合格最高点で受かるという偉業を成し遂げた人がいたんです。あるときその先輩に「どうやったら、そんなによい成績が取れるんですか」と尋ねてみたんですね。すると、「勉強記録をノートに付けるだけだよ」と。自分が何を何時間勉強したかをノートに記録して、グラフを作るだけ。やってみたら、これがものすごく効果があったんですよ。
記録して、グラフにして可視化するだけなんですけれども、「これだけ勉強した」という達成感や自信が得られたり、逆に意外に勉強していないことがわかって、だったらどうしようかと、目標を定め、計画を立て、実行するということが自然とできるようになったんです。学習記録をつけて進捗管理をすることがいかに大事か、実感しました。
受験勉強に限らず、勉強というものはモチベーションが鍵だと思うんです。長期間にわたって高いモチベーションを保って、勉強量を積み上げられるかどうかが、結果につながる。しかし、それが難しい。
学習を継続することが、学習する人にとって一番大きくて普遍的な課題なのだとしたら、そこを支援するサービスはビジネスとして成り立つのではないか。私自身の原体験として、勉強記録をつけることの効果は実感していましたので、自分がそこを解決しなくてどうする!と、勝手に使命感のようなものを感じて始めたというのが、「Studyplus」誕生の、そもそもの始まりです。
「学習記録をつけるだけでモチベーションが上がる」と聞いても、本当なの?と疑ってしまうかもしれません(笑)。
そうですよね(笑)。でも実際、リリース直後から、「三日坊主だった自分が、勉強を続けられるようになりました」「志望校に受かりました」といった、たくさんの感謝の声をいただいていて、自分の原体験も合わせて、このサービスの価値、方向性は間違っていないという確信はもっていました。
「測定なくして改善なし」と言われるように、記録をつければ自然と見返すでしょうし、そこから気づくことって、必ずあると思うんですね。
たとえば、「得意な英語ばっかりやっちゃっているけど、苦手な数学をやる時間を増やしたほうがいいかな」とか、同じ科目でも単元によって得意不得意があると思うので、「次の模擬試験までにこの単元の苦手を克服するには、この教材をここまでやっておこう」とか、記録をつければ問題点や改善点が明らかになって、それを解決するための目標や計画が立てられる。さらに、スケジュール通りにちゃんと進んでいるかも一目でわかりますから、学習の進捗管理やペースメイキングも自分でできるようになる。しかも、アプリで簡単に記録がつけられますから、私がノートにグラフを書いていたのよりも、はるかにやりやすい。とりあえずはだまされたと思って、記録をつけてみてほしいんです。やってみれば、記録をつけることの楽しさや意義や効果といったものがわかってくると思います。
アウトプットの量を増やし、わからなかったらインプットに戻る
今回の特集テーマである「インプット・アウトプット」という観点から学習マネジメントをするとしたら、どんな点に留意すればよいと思われますか。
インプットしたらすぐにアウトプットすることが大事だと思いますね。授業を受けたりテキストを読んだりしたら、すぐに問題演習をする。それでわからない問題があれば、解き方や答えを見て、またインプットに戻ればいい。よく、「最初に過去問をやるといい」などと言われますけど、一度「こういうふうにアウトプットするんだ」とわかってからインプットに戻ると、より効率的にインプットができるはずなんですよ。
とにかく、わからなければインプットに戻りつつ、問題演習(アウトプット)の量を増やしていくと、すごく身につくと思います。また、記録をつけていると、インプットやアウトプットのどちらに学習が傾いているか、きちんとインプットとアウトプットをセットにして学習が行えているか、ということもわかります。
「Studyplus」をうまく使っている人の声には、「勉強時間が伸びた」というものも多いようですが、やはり、学習時間は長いほどよいものでしょうか。
私自身、こと受験勉強に関してはシンプルに、学習時間に比例する形で成績が伸びると思っています。
もし、すごく時間をかけているのに成果が出ないとしたら、教材が合っていない可能性があるので、いったんその教材はやめたほうがいい。自分の学力にちょうどいい教材を選んで、それをひたすらやる、量をこなす、というのがおすすめです。
「Studyplus」を使っていると、学習時間がグラフになりますから、その記録をどんどん伸ばしていきたくて、学習時間が結果的に伸びていく…という効果がありますが、そのほかにもSNSの機能を使って、同じ志望校の人たちと交流したり、ほかの人がどんな教材を使ってどんな時間配分で勉強しているのかを見たりすることができます。そこから、自分が使う教材や勉強のしかたや勉強時間を見直して、学習方法を改善していくことが、自らできるようになっていくと思います。
SNS機能をうまく使えば、モチベーションUPと学習の継続に効果大
手書きの学習記録ノートにはなかったSNS機能ですが、あるのとないのとでは、大きな違いがありますか。
人の気配があるというのは、学習の継続という面でもすごく大きいと思います。
勉強って、基本的には孤独な闘いで、孤独ゆえに挫折してしまう、継続できないということが多いと思うのですが、「Studyplus」の「タイムライン」を見れば、同学年の人、同じ志望校の人ががんばっているのが見えて、それで安心したり、励みになったり、あるいは競争意識をかき立てられたりもするわけです。また、自分の学習記録を公開すれば、ほかの人から「いいね」が付いたり、コメントでほめてもらえたり、励ましてもらえたりもする。
学校によっては、同級生と受験や勉強の話がしにくいという人もいますし、たとえば社会人で資格取得を目指して勉強している方などからも、「Studyplus」に来れば同じ目的をもった仲間とつながることができるからうれしい、という声を聞きます。「うまく使う」ことが前提になりますが、SNSも活用すれば、より楽しく勉強ができたり、モチベーションを高く維持するツールになると思うんですね。
実際、「Studyplus」もSNS機能を内蔵してからの方が、ユーザーの継続率は段違いに高くなりましたし、新規ユーザーの数も段違いに増えました。
今や、累計会員数700万人以上、日本の受験生の2人に1人が利用するアプリに成長した「Studyplus」ですが、まだ進化していく可能性はありますか。
2022年1月から、デジタル教材を「Studyplus」上で使える「Studyplusブック」という電子参考書プラットフォームの提供を始めました。
今はまだ過渡期ですけれども、今後必ず「デジタル学習時代」となり、紙媒体の教材から、参考書や問題集、映像授業、AI教材など、いろいろなものがデジタル化していくはずです。ですので、それらすべての学習が「Studyplus」上でできて、しかも自動的に学習情報が記録されて、一元管理ができるような形を目指しています。
これは単に学習者の自己管理のためだけではなくて、一元化された学習記録が学校の先生や塾や予備校の先生にも共有されれば、それを元に効率的な指導やアドバイスをしてもらうということができるんじゃないかと思うんですね。「Studyplus」にはまだまだ、進化、発展の余地があるので、今後の展開にも期待していただきたいです。
「学び」の継続を習慣化できたら、それは一生の財産になる
最後に、廣瀬さんは「学ぶ」ということをどのようにとらえていらっしゃるか、教えていただけますか。
そもそも「学ぶ」って何だろうと考えたとき、私は「学ぶことは変わること」だと思っているんです。
世の中には、自分には理解できないもの、知らないものがたくさんあります。それを「学ぶ」ことで、学ぶ前の自分と、学んだ後の自分は変わる。どう変わるか、その変化に価値があるのかどうかなんて、やってみなければわからない。でも、そこには希望があると思うんですよ。過去や現在の自分がどういう状況だとしても、「学ぶ」ことで未来は変わる、変えることができる。自分の枠や可能性が広がる。
変化が激しく、予測不能な現代を生きるうえで、自ら学び続け、変わり続けられる人であるかどうかは、とても大事です。
だからこそ私は、「Studyplus」というプラットフォームを使って、「学ぶ」ということをもっと楽しく、もっと自由なものにしていきたいんですね。楽しんでやっていたら、いつの間にか時間が経っていた――そんな「学び」を続けていってほしい。自らをマネジメントして、楽しく、モチベーションを高く保ちながら「学び」を継続するということが習慣化できたら、それは一生残る財産ですから、私たちはそれを支援していきたいと思っています。
ありがとうございました。

Studyplusとは
Studyplusは、勉強した日時や時間などを簡単に記録でき、学習内容をグラフでも確認できる、受験生を始めとする中高生に人気の無料の学習管理アプリです。スマートフォン版のほか、PCからも利用できます。
このアプリを使うことで、「どのくらいの時間、何を勉強したのか」「いまの自分がすべきことは何なのか」がひと目でわかり、学習計画を立てるのに役立てたり、参考書などの学習ツールを管理したりすることができます。
Z会では、大学受験生向けコースに「Z会合格アシスト」をご用意。Z会の教材とStudyplusを連携させ、利用することができます。
※「Z会合格アシスト」は、Z会大学受験生向けコースの本科、共通テスト攻略演習、東大即応演習、京大即応演習、受験小論文コースのいずれかをご受講いただいている方向けのサービスとなります。
※Z会グループは、スタディプラス株式会社と業務提携契約を締結しています。

スタディプラス株式会社 代表取締役
廣瀬高志さん
1987年生まれ。私立桐朋高校卒業。
2010年、慶應義塾大学法学部在学中にスタディプラス株式会社を創業、代表取締役に就任。2012年に学習管理アプリ「Studyplus」をリリース。累計会員数700万人以上、日本の受験生の2人に1人が利用する教育アプリ利用者数No.1のサービスに成長。
Studyplus

