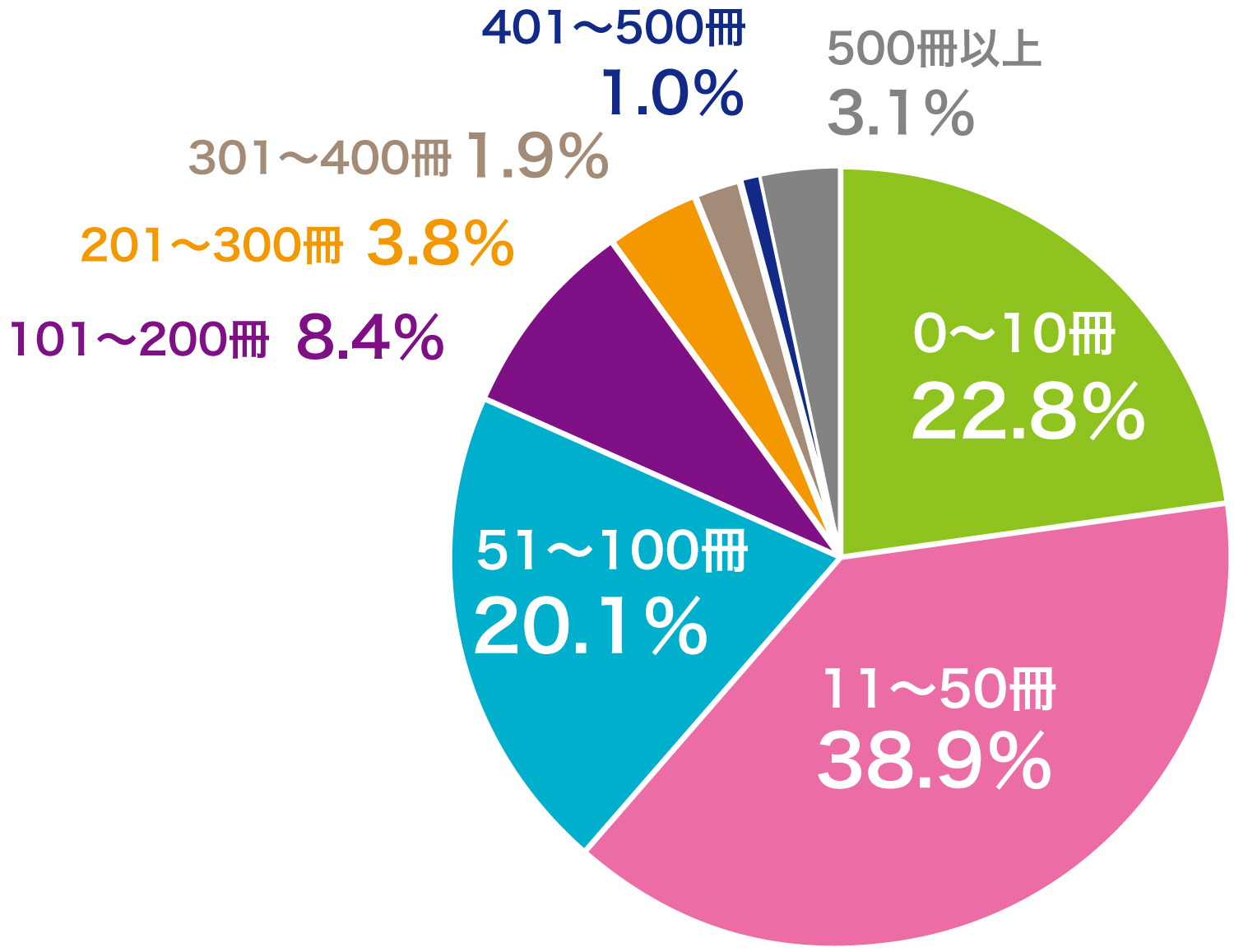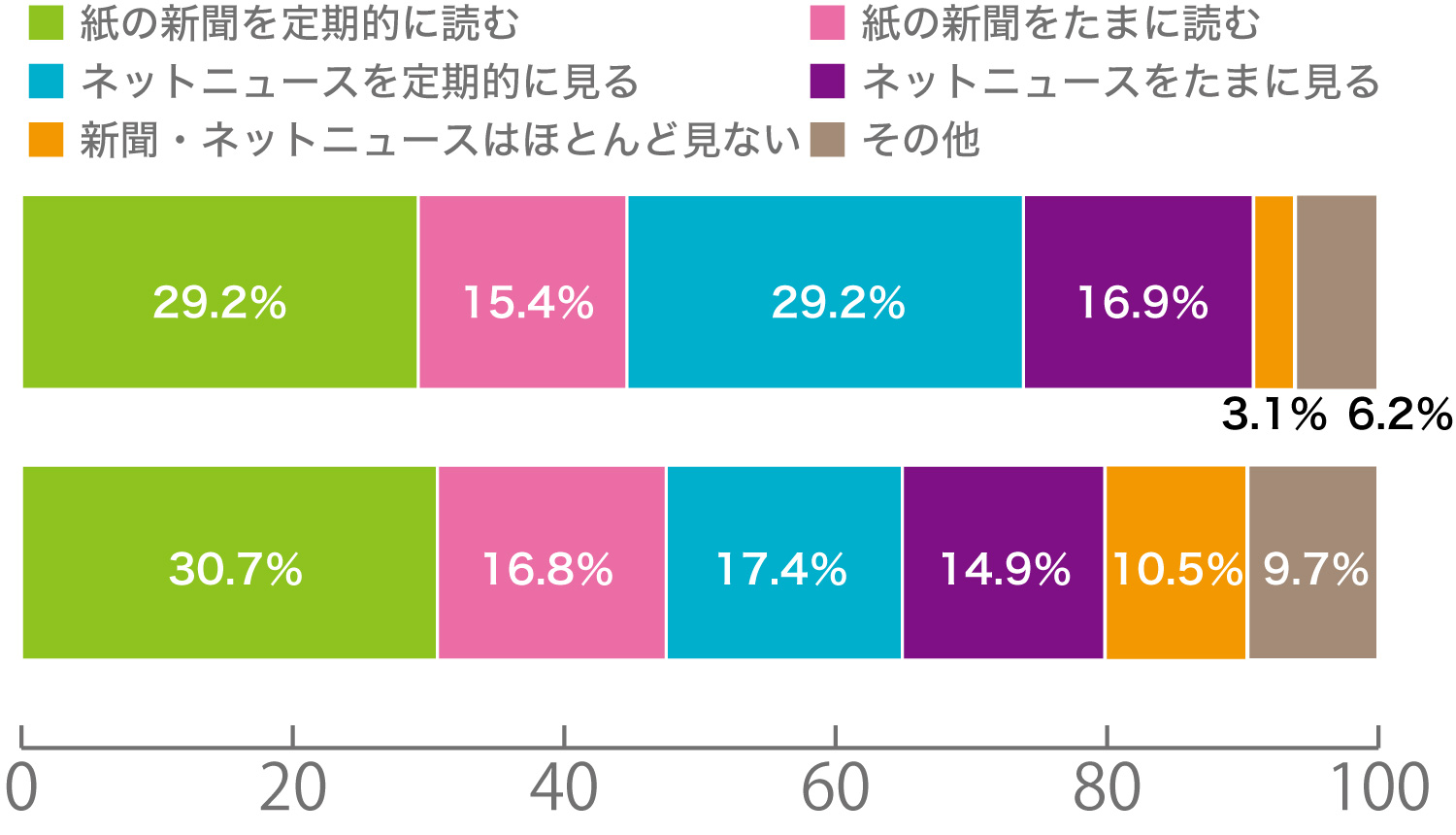読書と読解力の関係は?
読解の4つのステップ
- 1.文字を音に変えてそのまま読み上げることはできるけれど、意味としてはよくわかっていない「文字を読み上げる」だけの段階。
- 2.書かれている文章の世界に閉じた範囲で理解したという段階。
- 3.自分が持っている知識やこれまでの経験を使って推論も含めて理解したという段階。
- 4.持っている知識やほかの情報などをふまえて、書いてあることが本当かどうか根拠に照らし合わせて考え判断することや、書いてあることを却下するというような意思決定ができる段階。
―ところで、読書は読解力の向上に寄与するのでしょうか?
はい。読書と読解力の関係を探るさまざまな研究を見ると、ざっくりと、本を読んだ方が読解力が上がるという関係性があると言えます。ただし、読書量や時間よりも、「楽しんで本を読む習慣があるか」「さまざまなジャンルの本を読むか」など「何をどんなふうに読んでいるか」という調査の方が、読解力を測る指標との関連が出やすいようです。したがって、嫌々読むことにあまり期待できないと考えられます。嫌々読む場合、ただ読み上げるだけでになりがちなので、2段階目や3段階目の力につながりにくいのだと思われます。
―楽しんで読む習慣や多様なジャンルの本を読むことは、読解力の向上とどのように関係しているのでしょうか?
楽しんで読むには本の内容を理解しないと楽しめないので、書いてある情報を整理して頭の中に情報のつながりをつくり上げていくということをたくさんすることになるため、2段階目、3段階目の力につながると思います。
また、さまざまなジャンルの本を読むことも大切です。文章はジャンルによって構造が異なっています。たとえば、物語文の多くは、初めに設定があって、何か出来事が起こり、その解決に動くというように因果で話が進みますし、多くの場合時系列で書かれています。それに対して説明文は、まず大きな概念が示されて、それについて具体例で説明されることがあれば、2つの事例を比べるという比較の構造が用いられるなど、いくつかの構造化のタイプがあります。そういった文章の「枠組み」と言えるものがジャンルごとにあるので、枠組みの存在を知っていると、文章を読むときにその枠にあてはめながらある程度の目論見をもって読めるので、読むのが楽になります。
さまざまなジャンルの本を読んでいると、枠組みを知る機会が増えます。ですから、たとえば、ライトノベルだけを読んでいる人が新書を読むとなると、枠組みが違って読んでわかるまでに苦労しますが、ライトノベルも新書も読む人であれば、科学的な論考を読まなければならなくなったときに知っている枠組みを使って読める可能性が高いなど、読みやすさが変わってくることが考えられます。
また、ボキャブラリーの獲得という点でも、幅広い分野の本を読んでいると、ボキャブラリーが増えて次の本を読むときの助けになります。そして、次の本でまたボキャブラリーが増えて、と、読める本やわかる内容が増えていくことにつながっていきます。
―ということは、幅広い分野の本を読んだ方がいいのでしょうか?
本を読むという行為自体は、読解力を高めるためにするものではなくて、楽しむためや、好きですることだと思うので、無理やり読むことは先ほどお話ししたようにあまりおすすめしません。
本を読む習慣がない、あるいは、読書は好きでないけれど、読解力はつけたほうがいいなと思う人は、どんな本でもいいので、読めそうな本から読み始めるのがいいと思います。本でもマンガでも、自分が興味が持てる本をたくさん読んで、まずはその中に出てくる言葉をたくさん吸収していきましょう。すぐに読解力テストの結果に結びつくわけではありませんが、ボキャブラリーが増えることが読解力の向上にマイナスに働くことはありません。
あとは、仲の良い友達から好きな本を貸してもらうとか、友達と一緒に読んで話ができる本があると、すごく楽しくなると思います。そして、読んだらその本について語り合う。最初は「最後のほうエモかったよね」などシンプルな感想でもかまいません。そこから「そうそう、あのシーンがエモかった。なぜならこうだったから」などと説明し合う中で内容をつかむことが促進されていきます。だれかに内容を伝えなきゃ、教えてあげなきゃ、となると真剣に読みますよね? それはすごくよい読解力のトレーニングになりますよ。
デジタルの世界の情報の読解に必要なこと
―ここまで、文章の読解力に焦点をあててお話をうかがいましたが、インターネット上の情報を読む際も読解力が求められるかと思います。読解に必要なことや鍛え方を教えてください。
まず、インターネット上の情報の読解については、この3〜4年くらいの間に注目が高まり、「読んでわかる」だけでなく、不正確な情報を見抜くなどメディアリテラシーともいえるところまで踏み込んで読解ととらえる雰囲気が強まっています。それに伴い、「デジタル読解」という言葉も生まれています。
背景には、インターネット上の情報は質が多様で、かつ、大量なため、情報を選び取る力がより一層必要とされることがあります。テキストだけでなく、映像や、音・アニメーションを含んだ動画など、さまざまな形の情報が含まれていますし、見知らぬ他者の意見が常に複層的に流れ込んでくる中それらをいかに整理し、自分の中で一貫した知識にしていくかはとても大変です。
―どのように読んでいくといいのでしょうか?
今のところ、デジタル読解の方略も、それを教えるためのカリキュラムも、体系化されたものは確立していません。「センセーショナルなタイトルの記事は割り引いて考える」「検索結果の最初の数個だけを見るのでなく、2ページ目や3ページ目も見て、複数の記事をプリントアウトして比較しながら読む」といった具体的なコツはいくつか提案されています。疑わしい情報の真偽を検証するファクトチェックの方法として実践されている読み方も参考になりますね。
読解力は「幸せに生きる」ために必要なこと
―なぜ、私たちは「読解力」を身につける必要があるのでしょう?
少なくとも現状においては、契約書、説明書、新たな技術についてのマニュアル、役所で申請を行う際の書類や説明資料など、大事な情報はだいたい文字になっています。この点から、今の世界で生きていくには、自分にとって難しい単語や、知らない知識について書かれている文章を正確に把握しないと、クオリティ・オブ・ライフが損なわれたり、生命の危機にさらされる場面がたくさんあるということがわかると思います。健康で幸せに生きていくには、「読んでわかる」ことができなければ困ったことになるというわけです。
そのために、説明文を読むときは基本的な方略を使いながら読むこと、日頃から内容を人に説明することに取り組むこと、たまにはより難しい文章にもチャレンジすること、自分が知っている知識を使って読むくせをつけることなどを積み重ねることが、とても大事な基礎トレーニングになります。ぜひ今から実践してください。
私は、本を読むことには2つの効能があると思っています。1つは、先ほど述べたように健康で幸せに生きていくためには「読んでわかる」ことができないと困る、という意味で読解力を鍛えられること。もう1つは、日々、目の前を見ていただけでは見えない世界を見せてくれること。「あ、こういう世界もあるんだ」「生きていくってすばらしい」「生きていくってつらい」といったことを知り、世界を押し広げてくれるのも読書の効能です。読解力の向上に役に立たないかなと思う本であっても、大好きな本や読みたい本があることは、ぜひ大事にしてほしいと思います。
また、2つのうちのどちらかだけを重視するのは、もったいないことだとも思います。たとえば、「読解力とかどうでもいい、私はこの自分の世界を広げてくれる好きな本だけを読んでいくんだ」「なんでこんなつまらない本や文章を読解力向上のために読まないといけなんだ」といった考えの人は、とはいえ生きていくには説明的な文章を読んでわかるようになることは大事ですから、読解力を鍛えないといけないときはがんばってほしいですし、逆に「読解力の勉強としてしか本や文章は読みたくない」という人には、自分の世界を広げるような読書もいいものですよと伝えたい。どちらも意味のある読書だということは、みなさんに意識していただけたらうれしいです。