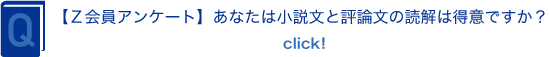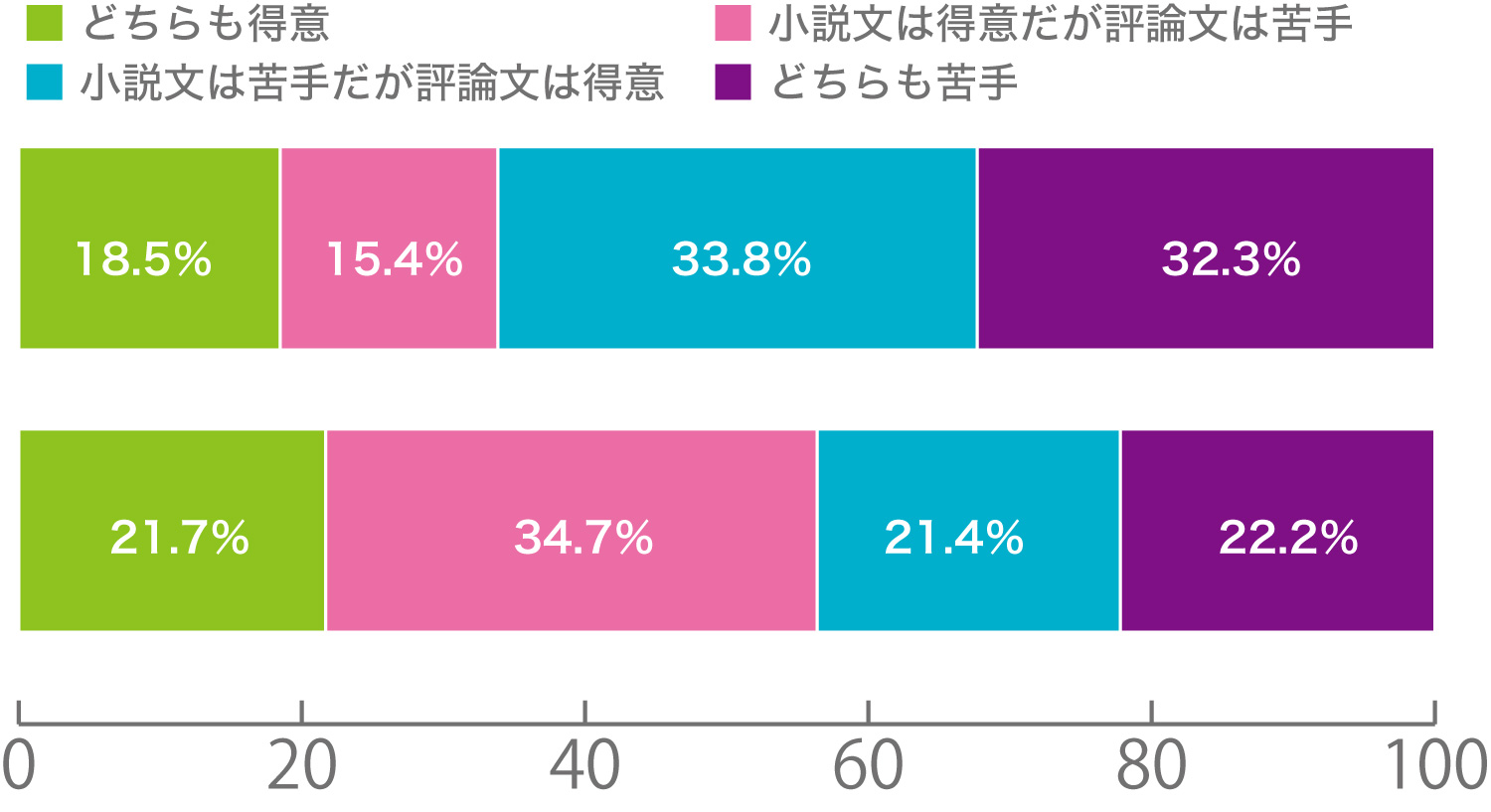「読解力」を鍛える3つの方法
―では、そのような読解の力はどうやって鍛えていけばよいのでしょうか? 具体的な方法を教えてください。
私の研究対象はおもに説明文の読解なので、説明文の読解力を鍛える方法についてお話しします。おすすめの方法としては、「ボキャブラリーを身につける」「方略(読み方)を使えるようになる」「メタ認知を高める」の3つが挙げられます。
まず、「ボキャブラリーを身につける」ですが、言葉の知識は読むことをスムーズにすることは、みなさんも経験から何となくわかるのではないでしょうか。
読んでいて知らない言葉に出くわすたびに調べるのは面倒ですし、調べているうちにそれまでに把握していた文章の全体像がわからなくなって全体理解が損なわれやすくなります。
読解に重要なボキャブラリーには、「キーワードのボキャブラリー」と「学習用ボキャブラリー」の2つがあります。
「キーワードのボキャブラリー」とは、あるトピックについて関連する言葉のこと。たとえば、数学なら「垂直」とか「比例」といった用語が該当します。こういった用語をたくさん知っているほど、読んで理解することがしやすくなります。
「学習用ボキャブラリー」とは、日常生活では使われにくくて意味を覚える機会が少ないけれど、いろいろな文脈で新しい言葉を覚えるために重要な言葉のことです。たとえば、「立場」「流れ」「面」「あるいは」「さらに」「およそ」「応じる」「関する」「成り立つ」など。これらの言葉は、大人や本を書いている人は「きっと読んでいる人もわかるだろう」と説明なしに、なにげなく使いがちです。ですが、子どもたちは日常生活ではあまりこうした言葉を使わないですよね。意味をとらえた言い換えができるか確認するなどして、学習用のボキャブラリーも身につけられるよう、大人のサポートも必要です。
―2つめの「方略(読み方)を使えるようになる」とはどういうことでしょうか?
「方略」とは、読んで理解するために意図的にやることや考えることを表す心理学の言葉で、英語の‘Strategy’を訳したものです。「読むための戦略」とも言えるでしょう。そして、読解方略を使って読むことで理解度が向上することが、さまざまな研究からわかっています。
これまでの研究で「実際に多くの人が採用している読み方で、内容がよくわかる効果がある」とわかっている方略には次の6種類があります。まず、やりやすそうなだなと思えるものから使って読んでみましょう。
- ①基本的な読み方コントロール
あれ?と思ったらゆっくり読む/わからないと思ったら何回か読んでみる - ②明確化
「コレ」「ソレ」などが何を指しているかはっきりさせる/あいまいな表現のものをつまりどういうことか言い直す/はっきり書かれていないことを足して言い直す/自分の言葉で言い直す - ③要点把握
大事そうなところを見つける/キーワードを見つけて目立つようにする/だいたいどういう流れなのか図にする/箇条書きにする - ④理解チェック
わからないところはどこか考える/自分がちゃんとわかっているか確認する/先生ならどんな質問をするか考える - ⑤構造注目
文章の段落構造に注意する/接続詞に注目して話の流れをとらえる/いくつかのまとまりを作って整理する - ⑥知識の活用
関連することで何か知っているか思い出す/知っていることと同じところ、違うところを考える/知っている内容と結びつける
―こういった方略はどうやって学べばよいのでしょうか?
一つは、国語の授業を活用することです。先生方がはっきりと「これは方略です」とおっしゃらないことも多く、気づきにくいのですが、実は、国語の授業でも方略を習っています。たとえば、「この段落を300字で要約しなさい」という問いは「要点把握」を、「『これ』は何を指していますか?」という問いは「明確化」を練習する重要な機会です。授業でも方略を使った読み方を教わっているんだという意識をもって授業やテストに臨むといいと思います。
また、1人で方略を学び、身につけるのは大変なことですから、友達と一緒に取り組むのもおすすめします。友達と「キーワードに線を引く」という方略を使って個々に文章を読んで、どこに線を引いたか確認し合うのはどうでしょう。そのほかにも、読んだ本の内容を要約して伝えあったり、読んで理解したことを説明し合ったりするのもおすすめです。
あとは、学校などで「読んでまとめなさい」「読んだ内容をプレゼンしなさい」という機会があれば、意識して方略を使いましょう。その結果「その説明わかりやすかったよ」と先生や友達からフィードバックがもらえれば、うまく理解できていたととらえていいと思います。
このように、人と一緒に学習するとモチベーションが続きやすいので、なるべく仲間を見つけたり、家族の協力を得て取り組めるといいのです。1人で取り組む方法としておすすめなのが、読んだ文章や本の要約文や紹介文を書くことです。アウトプットすることは、読んだ内容をもう一度整理することにつながりやすいので、読解力を鍛えることになります。本のレビューサイトや口コミ欄に要約や魅力をまとめてアップするのもよいですね。
「方略を使って読む」ことは、大学進学以降も必要とされます。というのは、大学の先生たちは、みんな方略を使えるだろうと考えるので、方略を教えずに教科書や参考文献を指定して「ここまで読んできてね」と指示を出すことが多いのです。また、仕事をする中で新しい知識を獲得しなければならないときにも、うまく方略を使って内容を理解することは必要ですね。ですから、方略を使うことを受験のため、学校のテストや課題のためと思わず、さまざまな場面で意識的に方略を使って読むことに取り組んでほしいですね。
―3つめの「メタ認知を高める」とは、どういうことでしょうか?
メタ認知とは、「一段上の」という意味の「メタ」という言葉と、「知的な活動」を指す「認知」という言葉が合わさった言葉で、自分の知的活動を一段上から把握する頭のはたらきを指します。たとえば、文章を読んだり問題を解いたりしているときに「よくわからないな」と思うのもメタ認知です。自分はこれが理解できていないということを、自分で把握できているということです。このメタ認知を鍛え、はたらかせることで、文章を読んだときに「わかったかどうか」「どこがわからないのか」などをチェックし、わかっていなければ次にどうすればいいのかと考えることができるのです。
―メタ認知を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか?
おすすめは、こちらも友達の力を借りることです。メタ認知は基本的に甘いもので、私たちは、本当はわかっていないのを見逃して「わかったつもり」になりがちです。また、読むときには、読んで理解するという認知レベルの活動と、理解できているかどうかをチェックするというメタレベルの活動を同時進行しているため、その点でもわかっていないことを見逃しがちです。
そこで、文章を読んでわかったことを説明する「説明役」と、その説明にわかりにくいところがないかを厳しくチェックし、わからないところがあれば質問する「質問役」を自分と友達とで交代しながら読むことをやってみましょう。説明役として内容を説明しようとすると、モヤモヤしていたりあいまいだったりするところが明確になります。わかったつもりだったけどどうもよくわかってなかった、と気づいたり、あらためて頭を整理することが理解促進につながります。また、質問役として相手の説明のどこがわかりにくいかを把握し、あいまいさを明確にするための質問をすることで、自分が読むときにもうまくメタ認知をはたらかせられるようになります。