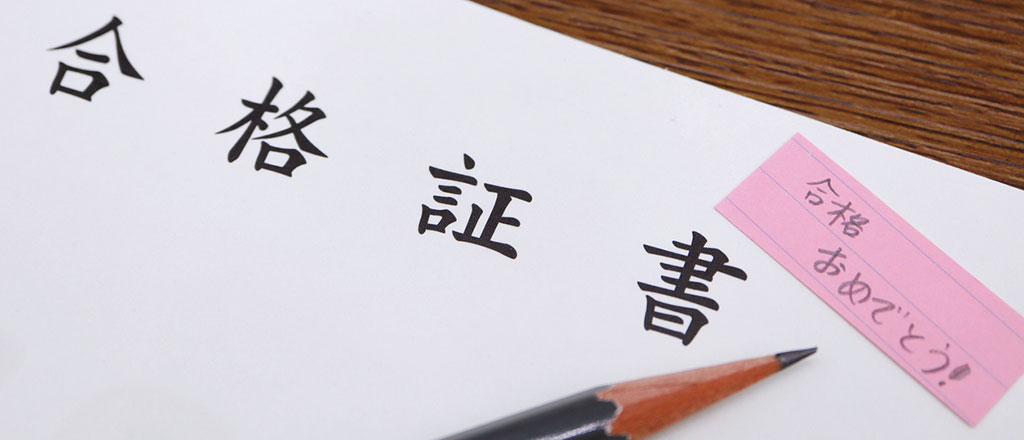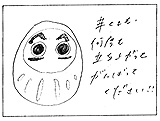過去問にとりかかるとき
私が過去問に本格的にとりかかったのは高校3年生の春休みです。公立高校で受験に必要な範囲を全て網羅していたわけではありませんでしたが、1年後に辿り着かなければならない目標地点を自分で知るために最新年度の1年分を解きました。もちろんその時点ではほぼ解けませんでしたが、英語の文章や国語の現代文、数学の1問くらいはなんとなく解ける部分もあり、自分に足りない基礎的な部分や今の知識をどう応用したら解けるようになるのか実感することができて、モチベーションも上がりました。過去問を最後にとっておく人もいますが、本格的な受験勉強に取り掛かる前に、勉強方法がブレないためにも軽い気持ちで解いてみるといいと思います。
過去問演習のエッセンス
僕は過去問演習を高3の9月ごろから始めました。演習には教科別に入るようにし、いいタイミングで参考書が終わった数学から入り、ワンランク上の問題集と同時並行で進めました。11月からは国語と英語、センター試験の後に日本史の論述の過去問を始めました。これらの科目は全て学校の先生の添削を受けるようにし、解答の必須ポイントとなる設問意図(この問いは何を求めているのか)を見抜くことを意識して取り組むようにしていました。また、復習などは添削が返ってきた後にすぐに行うようにし、あまりにも解答とずれている問題はもう一度添削を受け、自分の読みの修正を図るようにしました。時間配分はセンター試験の前まで意識せず、ポイントを正確に漏れなく盛り込むことに重点を置いていました。
自分にあった問題傾向を知る
自ら過去問に取り組むようになったのは高3の春頃です。最初は旧帝大や難関国立大と呼ばれる大学の過去問をひたすら解きました。結果的に自分には九大の問題が合っていると気づき、その後は九大に絞っていました。しかし私が通っていた高校は授業中に入試問題を解かせることが多く、九州の高校だったので特に九大の問題には低年次から触れることが多かったように思います。よって過去問に取り組んでいた時期は正確にはもっと前かもしれません。大学によって試験問題の傾向は全く違います。例えば同じ生物の試験でも知識力や計算力が問われる系、読解力が試される系、ひたすら記述させる系、時間勝負系など様々です。まずはいろいろな過去問を解くことで、自分にあったタイプを知ることが大事だと思います。
思いついた時から
過去問をいつから解き始めるか。受験生にとっては永遠のテーマですが、答えは簡単です。今、この瞬間からです。演習用として直前まで手をつけない派もいるようですが、私はあまりオススメしません。過去問は最高の演習問題であると同時に、受験勉強の指針を示す道標でもあるからです。どの分野を重点的に学習すべきなのか、答案作成においてどのような視点が必要かなど、インプット学習において不可欠な情報を得ることができます。また、過去問に何度も触れるうちに、次に問われそうな分野や範囲がなんとなく予測できるようになります。そうなってからが本当の受験対策です。教科書や参考書などに、出題範囲をまとめておくのもオススメです。
- 高2の春にほぼ解けなかった志望校過去問が、高3秋にはわりと解けるようになっていて、オープン模試でB判定をとることができました。夏にZ会の問題をたくさん繰り返し解いたからだと思いました。 (大阪大学・法学部 とうふ先輩)
- やってよかったことは、過去問研究です。夏に各学部(早大)1年分。秋に学部を絞り3年分。直前期に3年分をやりました。共通テストとセンター試験は違うと言われますが、傾向や特有の解き方、戦略を立てることに関しては一番の教材でした。やっておくべきことだったのは基礎固めです。 (早稲田大学・国際教養部 池ちゃん先輩)
- 高3の5月に1年分と高3の9月から10年分(英語は計27年分)の過去問をやりました。センター試験の過去問や共通テストの予想問題をちゃんと時間を計って解いておくと本番の練習になります。 (東京大学・文科三類 さあや先輩)
- まずは得意な科目の英語から手をつけました。学校で使う教材以外に取り組むように心がけ、難易度高めの問題集や過去問に挑戦しました。過去問は高2の夏に初めて解いて、高3の春から本格的に始めて、5年分に取り組みました。 (広島大学・教育学部 Yui. 先輩)
- 最初に過去問を解いたのは高3の春。最終的に10年分は解きました(教科によりバラつきはありますが)。一度過去問を解いて自分の弱点を見つけ出し、その克服のためにどんな勉強をすればよいかその道筋を明確にしました。 (東京大学・文科二類 T.Y 先輩)
- 得意だった英語は高3の6月から、国・理は夏休みから、苦手な数学は共通テスト後まで持ちこしました。教科により違うけど大体10年分の過去問をやりました。基本的に教科書の内容から出るので、過去問をやって間違えたところの教科書や資料集を読み込んだのがよかったです。ただ、得意科目を放置しすぎたのが反省点です。過去問をまずながめて、意外と基礎が多かったのでとにかく基礎に穴がないようにするというのを受験ぎりぎりまで続けました。 (東京大学・理科二類 めんだこ先輩)